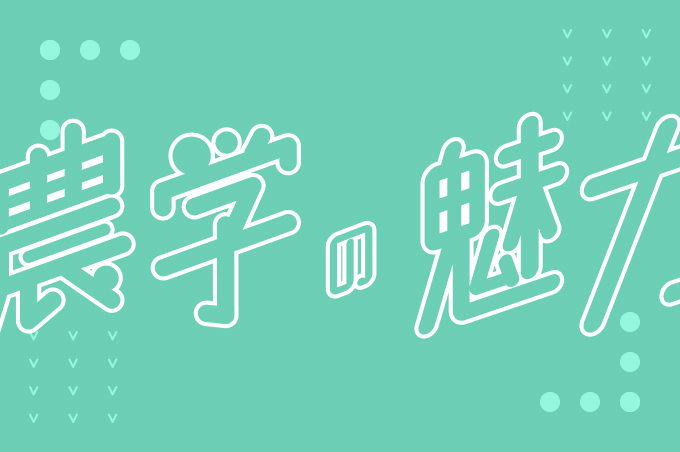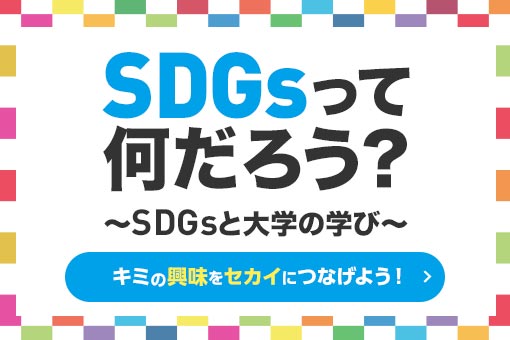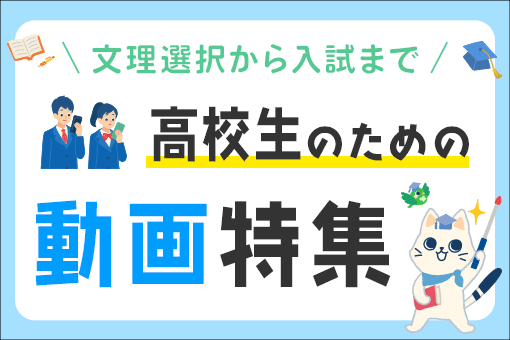ゴールが決まればやるべきことが見えてくる!秋から始める目標逆算型学習法

部活や勉強はもちろん、遊びでさえも、目標が決まると、やる気がわいてメリハリがつくものだ。今回は目標を決めることに慣れていない人に向けて、目標設定のメリットと、模試を例にした具体的な取り組み方を解説しよう。
「なんとなく取り組む」ではトップはねらえない
目標を決めるメリットは、ゴールが決まることで、「いつ・何をすべきか」が明確になることだ。勉強も部活も、なんとなく取り組んでいては、優れた成績は残せない。成功する人は、何事にも目標を立てて、計画的に行動しているものだ。
例えば、スポーツ選手にとって、目標設定は欠かせないもの。将来どんな選手になりたいか、どんな記録を残したいかを想像し、今の実力を分析して、今後の練習メニューを考えているはずだ。そうすることで、効率よく実力を伸ばせて、モチベーションも維持できる。
理想的な受験勉強の進め方も、実はこれに近い。志望校合格をめざして、時期ごとの学習到達度や目標偏差値を決めて、着実に力をつけるようにする。
この「ゴールを定めた逆算型学習」は短期間で身につけるのは意外と難しい。受験期になって慌てないためにも、今回は「模試」を用いた目標設定の仕方を紹介しよう。
模試の「目標設定」に挑戦してみよう!
目標を決めて取り組む身近な例としては模試がオススメ。具体的に、どんな方法を取ればよいのか見ていこう。
<STEP1> 志望校判定を1つ上げるのにあと何点必要か確認しよう
模試を受験した後、成績表に「合格可能性判定」が書かれているが、この合格可能性判定を確認して、1つ上の判定まであと何点必要なのか、総合点を確認しよう。例えば、C判定からB判定までアップするのに、あと40点必要だったとする。この点数を上げることを、次回の模試の目標に設定してみよう。
<STEP2> どの科目で何点くらい得点アップするかを決めよう
次に、決めた目標点をクリアするために、どの科目で何点取るかを決めよう。苦手科目を克服するのか、得意科目を伸ばすのか、前回の成績を見ながら考えていくとわかりやすいだろう。
<STEP3> 科目別にどの分野に力を入れるかを決めよう
最後に、次の模試までどの分野の勉強に力を入れるか、科目別に決めよう。「英語は点の取れていなかった英文法を、数学は苦手なベクトルを中心に」と決めておけば、どうやって勉強すればいいのか迷うことがなくなるはずだ。