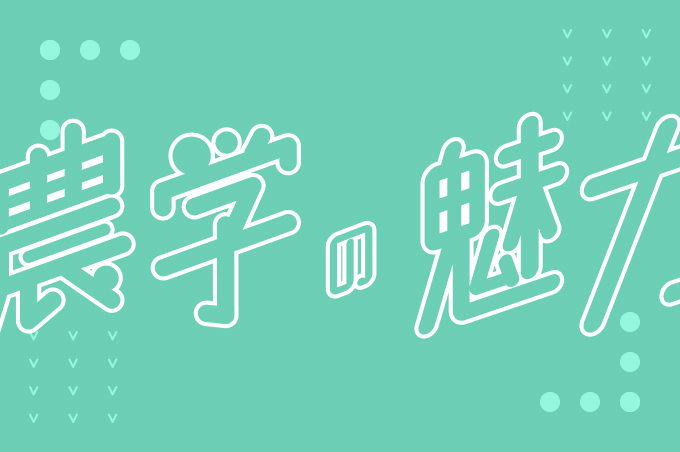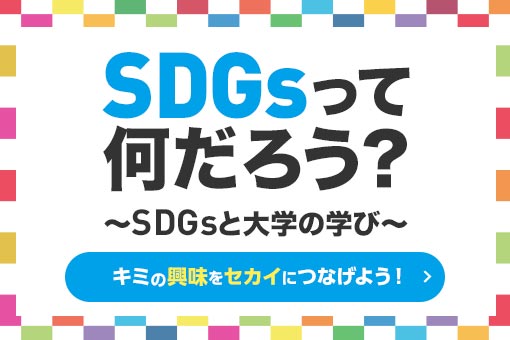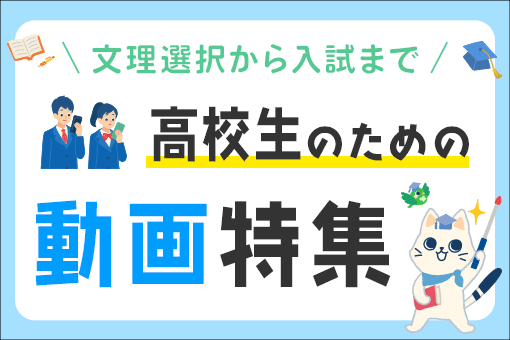<古文編>高校生のためのニガテ克服勉強法
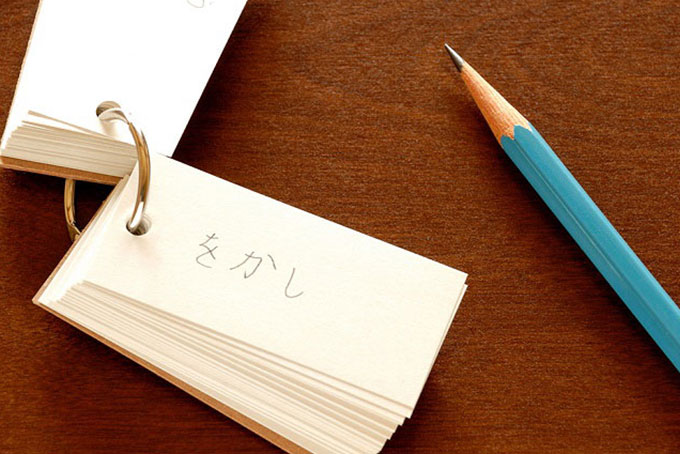
古文がニガテな人に多いのは、「文章を読んでも意味がつかめない」ことではないだろうか。古文文法の活用や古語の意味がある程度わかっていても、あらすじがつかめない人も多いだろう。今回は、そんな古文が読めないニガテを克服する勉強法を紹介しよう。
まずは登場人物を押さえる!
人物の敬語に注目して内容を理解しよう
文章を読むときには、「誰が、いつ、どこで、何をしたか」を正確に読みとることが大切。ここを押さえれば、大まかな内容はつかめるようになるはずだ。ただし、古文の場合は、主語が省略されていたり、文の途中で主語がかわったりするため、いつの間にかあらすじがわからなくなってしまうことが多い。
そんなときは登場人物同士の会話に注目し、敬語から発言者を特定するようにしよう。そうすると「ここに『まかる』という謙譲語が使われているから、ここの主語はこの人物だな」といった判断ができるようになる。会話のなかや前後に出てくる敬語に注目して「誰に対する、誰の発言か」を見抜くことで、内容がわかるようになってくるはずだ。
古典常識をストック!
当時の習慣や考え方を把握しよう
古文を読むには、当時の生活習慣や人々の考え方、物語のパターンを知っていると有利。なぜなら、古典世界特有の事項を知っておけば、行動や発言の意味にとまどうことが減るからだ。また、物語のパターンがある程度わかっていれば、文書を少し読んだだけで「次はこの展開になるかも」と予測できる。
このような知識は、授業で使っている便覧を読んでストックしていこう。古典の内容をマンガ形式で紹介した本を読んでみるのもオススメだ。
先輩はこう勉強した!オススメの予習法
最後に、授業の予習に生かせる勉強法を1つ、先輩の体験談から紹介しよう。
先輩の体験記

できるだけ細かく、文章を品詞分解する
古文のオススメ勉強法は、予習の際に細かく品詞分解をすることです。私は教科書の文章を品詞ごとに区切りながら、意味・活用・敬語の種類など、わかることをできるだけ細かくノートに書き込みました。初めは辞書が手放せなかったのですが、続けているうちにだんだんと品詞の見分け方が身についていき、助動詞の意味も自然と覚えられていました。面倒だと思うかもしれませんが、確実に実力を上げられる勉強法だと思います。