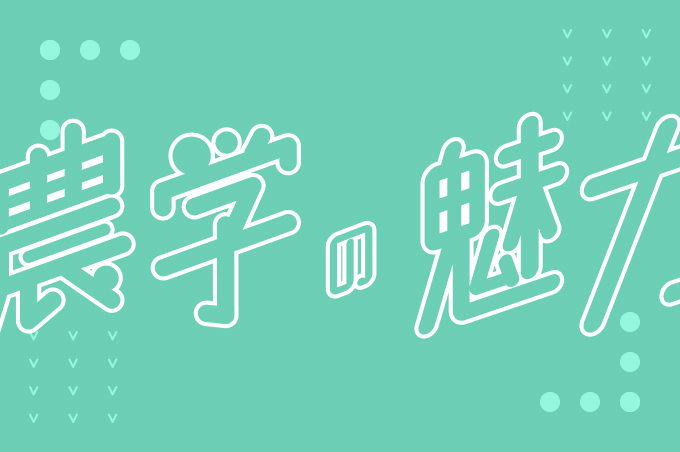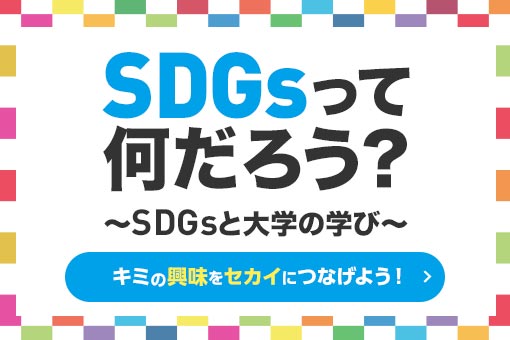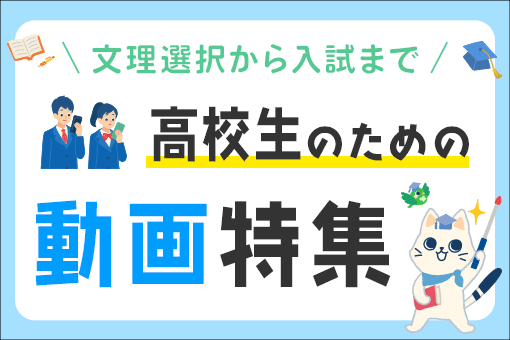これだけは知っておきたい! 大学用語辞典
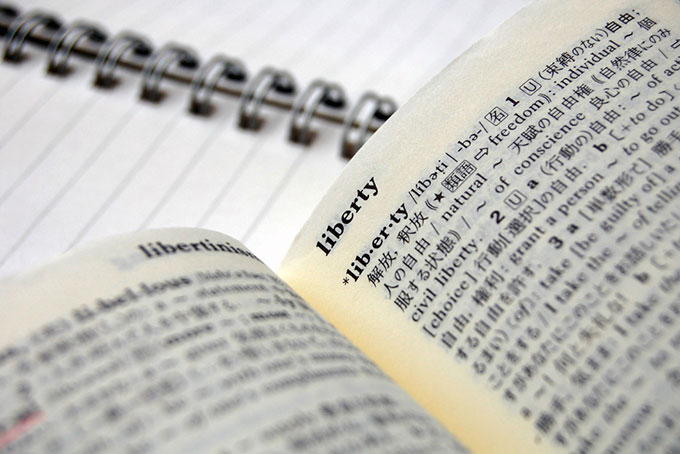
大学生活の準備を進めていると、見慣れない用語を見かけるはず。「シラバス」や「単位」といった用語の意味を、キミはちゃんとわかっているかな?数あるなかでも、特に知っておきたい用語をまとめたので、入学前に覚えてしまおう!
一般的な内容です。制度をはじめ、詳細は各大学の内容を確認してください。
あ行
一般教育科目
幅広い知識や教養を身につけるための科目のこと。主に1、2年次に受講することが多い。「基礎教養科目」「全学共通科目」など、呼び方は大学ごとにさまざま。一般教育科目に対し、学部・学科と関係の深い特定の内容を学ぶ「専門教育科目」がある。
eラーニング(e-learning)
学内外の端末からネットワークを通じてオンラインコンテンツを利用できる仕組み。活用方法やコンテンツは大学ごとに異なる。語学学習に利用することが多いほか、eラーニング上でレポートを提出したり、授業の資料をダウンロードしたりすることもある。
インターンシップ
企業や官公庁などで、自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験をすること。本格的な就職活動が始まる前に、夏休みなどの長期休暇を利用して参加するのが一般的。インターンシップを単位として認定している大学も多い。
オフィスアワー(制度)
学生からの質問や相談に応じるため、教員が研究室などの指定された場所に待機している時間帯(制度)のこと。講義や学業に関する質問のほか、学生生活や進路のことなどについても相談できる。
オリエンテーション
新たな環境に慣れるための説明会や行事全般を指す。新入生向けのオリエンテーションでは、カリキュラムや時間割のつくり方、施設・設備の利用法についての説明などが行われる。そのほか、新入生同士の親睦を深めるイベントも。
か行
学士
大学を卒業すると授与される学位のこと。学問分野ごとに「学士(教育学)」「学士(経営学)」「学士(理学)」などと表記される。学士のほかにも、「修士」「博士」の学位がある。
カリキュラム
大学、あるいは学部・学科独自に、学生に身につけさせたい教育内容を体系的に編成した教育計画のこと。大学の講義はカリキュラムに沿って用意されており、必修科目以外は学生が自ら受けたい講義を選ぶことができる。
キャリアセンター
学生のキャリア形成をサポートするための部署。就職活動についてのガイダンス、インターンシップのあっせんのほか、低学年次からのキャリア指導、資格取得の支援などを行う。なお、部署名は大学によって異なる。
休講
担当教員の都合や各種のトラブルによって、講義が休みになること。後日、休講となった講義を補うため、通常の時間外に補講が実施されることが多い。
教授
大学の教員のなかで、最も位が高い職務上の階級のこと。教授以外にも「准教授」「講師」などの教員が、講義や研究活動を担っている。特に功績のあった教授には「名誉教授」の称号が与えられることも。
掲示板
大学構内にある掲示板のこと。時間割、教室の変更、休講情報、留学情報、学生の呼び出しなど、重要な情報が掲示される。近年は電子掲示板(Web掲示板)の併用が進み、学生ポータルサイトを介して通知する大学が多い。
研究室
卒業研究(卒業論文)を進めるために所属する部屋であり、教員の執務室でもある。3年生の後半から4年生にかけて配属されるのが一般的。研究室内で実験する場合、実験結果が出るまで研究室に泊まり込むこともある。
コンソーシアム
複数の大学間の情報交流や研究交流などを通して、在籍する大学にはない分野の講義を受けられる仕組み。ただし、履修できる単位数や、認定される単位数などに制限が設けられている。
さ行
サークル
趣味や資格取得など、共通のテーマ・目的を持つ人が集まって課外活動を行う団体のこと。スポーツ系、文化・学術系のほか、特定のテーマを持たないオールラウンドサークルなど、大学ごとにさまざまな種類がある。
産学連携
民間企業と大学などの教育機関、研究機関が互いに協力し、共同研究や開発をすること。産学連携における共同研究は、大学の研究力と企業の技術力が結集する。そのため、授業などを通してその過程に携われる場合、学生にとって実践的な経験を積む機会となる。
シラバス
講義の要旨がまとめられたもの。講義名、教員(教官)名、取得単位数、講義の目的や進め方、取り上げるテーマ、教科書、テスト(評価方法)など、講義に関するさまざまな情報が記載されている。学生はシラバスをもとに、履修する科目を選択する。
ゼミ
ゼミナールの略称。専門分野に特化した少人数制の講義のこと。学生がテーマを設けて調査や実験を行い、発表、ディスカッションする。長期休暇の際は合宿があることも。
セメスター制
1年間を前期と後期の2つの学期(セメスター)に分ける制度。通年制に比べて短期間に集中して学習できる。また、講義が学期ごとに完結するため、後期は履修登録せずに留学する、といったことも可能。1年間を4学期に分ける制度は「クォーター制」と呼ばれ、広島大、南山大など導入する大学は増えている。
早期卒業制度
一定の条件を満たせば、3年間程度で学部を卒業できる制度のことで、一部の4年制大学で設けられている。また一部の大学院では、学部の3年次修了後に大学院に入学できる制度がある。ただし、この場合「早期卒業制度」を併用すれば大学卒業とみなされるが、同制度がない場合、学部は中途退学の扱いとなるので注意が必要。
卒業論文
研究活動の成果として、卒業年次に提出する論文のこと。文字数や形式は大学・学部・学科によって異なる。卒業論文の提出が卒業に必要な条件となっていることも多い。
た行
第二外国語
主要な外国語(多くの場合は英語)のほかに、2つ目に学ぶ外国語のこと。多くの大学で必修とされている。大学によって学べる言語は異なるが、中国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語などが多く見受けられる。
他学部聴講制度
所属する学部以外の講義を受けることができる制度。卒業に必要な単位として認められるケースと、認められないケースがある。
ダブルスクール
大学で勉強しながら、専門学校などでも勉強すること。めざす資格を大学在学中に取得するため、または公務員試験・司法試験などの試験対策のためといった理由が多い。
単位
授業科目を「単位」と呼ばれる学習時間数に分けて修得していく方式のこと。授業科目、実験、実習、実技ごとに取得できる単位数が決まっているほか、年次ごとに取得できる上限単位数も設けられている。一般的に、4年制大学では90分の講義を15週受講することで2単位を取得でき、卒業までに最低124単位を取得する必要がある。 授業科目ごとの単位数や年次ごとの上限単位数、卒業に必要な単位数などは、大学ごとに設定されている。
単位互換制度
協定を結んでいるほかの大学の講義を受けた場合、所属する大学の単位として認定される制度。自分の大学にはない分野の科目を学ぶことができる。ただし、履修できる単位数、認定される単位数には制限がある。
チュートリアル教育
教育手法の1つ。主に医学部、歯学部、看護学部などで行われており、与えられた課題に対して、学生は少数のグループで検討し解決していくスタイルが特徴だ。教員(チューター)は従来の講義のように知識を与えるのではなく、課題解決に向けて助言を与える役割。学生が能動的に学び、問題解決能力を養うことが期待される。
TA(ティーチング・アシスタント)
学生をきめ細かく指導するために、担当教員の指示のもと、授業を補助する人・役割のこと。主に大学院生が担当し、実験や実習などがスムーズに進むよう、サポートやアドバイスをする。
転部・転科制度
大学入学後、自分の進路に変化が生じた場合に、別学部・学科に変更できる制度。多くの場合、希望する学部・学科が提示する条件を満たしたうえで、選考試験に合格した場合に転部・転科できる。
は行
必修科目
大学で履修する科目のうち、卒業要件として必ず履修しなければならない科目。いくつかの科目から選択できる「選択必修制度」もある。これらに対し、自由に選べる科目を「選択科目」と呼ぶ。
フィールドワーク
テーマや調査内容を設定し、対象となる地域に出かけて調査などをすること。実地での体験や調べたことを通し、文献資料だけではわからない成果を得ることが目的。地理学、文化学、生物学、社会学など、多くの学問分野で実施されている。
副専攻制度
専門的に学んでいる分野(専攻)に加えて、興味がある別の分野も専門的に学べる制度。勉強は大変になるが、2つの分野の知識を同時に身につけることができる。
ら行
履修登録
学年や学期が始まる前に、自分が受けたい講義を事前に選んで大学に申請すること。シラバスで講義の内容を確認しながら選ぶ。人気の講義は抽選になることもある。