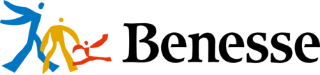学問分野辞典
興味のある学問を探すには、学問系統名をチェックし、「これが近そう」と思った系統の分野を見ていこう。
また、学びの内容や、学んでおきたい教科をチェックしておこう。
それぞれの学問が文系、文理系、理系のどれに当てはまるかは系統名の上に示してある。
- 日本文学
-
学びの内容
時代を問わず、日本語で書かれた物語、小説、短歌、戯曲などの文学作品を研究する。作品のテーマ、作家の経歴、当時の時代背景などを通して、作品の魅力や日本、人間そのものを知る研究だ。より深い研究では、日本の歴史や社会などもあわせて学ぶ。
学んでおきたい教科・科目国語は古文や漢文も含めてよく学ぼう。また、作品の歴史的・地理的背景を知るために日本史や地理に通じておくことは重要だ。多数の文学作品に触れておくほか、海外の研究事例を知るため英語力も身につけたい。
- 外国文学
-
学びの内容
諸外国の言語で書かれた文学作品を研究する。作品・作家や時代背景、国民性などを理解することに加え、原書を読むための作品が書かれている言語の習得も重要になる。その国や地域への理解を深め、作品の解釈を論じる。
学んでおきたい教科・科目作品を深く理解するために外国語を習得する。また、文献は英語が多くなるため、高校生のうちに重点的に英語に取り組もう。読解力や表現力を高める国語と、作品背景を理解する世界史や地理も重要。
- 哲学・倫理・宗教
-
学びの内容
洋の東西を問わず、哲学書や哲学者の研究を学び、人間やそれを取り巻く世界の本質を追究する哲学、社会や世界にとって、よりよき人とは何かを探求する倫理、宗教の教理の理解と信仰心を研究する宗教に分かれる。
学んでおきたい教科・科目読解力や思考力が必要なので国語力は高めたい。原書購読も多いため英語も必要だ。思想や宗教を把握するため世界史や日本史、地理は大事にしたい。論理的な思考を磨く数学も重要となる。
- 心理学
-
学びの内容
人間の心と行動を科学的手法で解明・研究する。臨床心理学や認知心理学、社会心理学、人格心理学など幅広い研究分野に分かれている。主な研究手法として行われることは、実験とそこから得られたデータの統計化・分析となる。
学んでおきたい教科・科目研究データを理解するため、統計などの数学は重要。実験・研究対象者とのコミュニケーションに生かされる国語、脳の働きなどを計測するため、基礎的な生物に対する知識も必要。文献講読のために英語も必要になる。
- 歴史学
-
学びの内容
各国の文献や古文書などの資料から実証的な研究を行い、歴史的事実を明らかにする。得られた結果から、現在の問題に対する解決策を見いだすことも歴史学の範囲だ。大学では主に東洋史、西洋史、日本史などに分かれる。
学んでおきたい教科・科目研究するエリアや時代がどこでも、日本とのかかわりが重要になるので、日本史と世界史は重要。資料を大量に扱うので国語、古い文献を読むため古文と漢文、海外の資料に目を通すために英語はきちんと学んでおこう。
- 考古学・文化財学
-
学びの内容
考古学では遺跡や遺物を調査し過去を明らかにする研究が行われる。文化財学では未来に残すべき遺跡や遺物、美術品や工芸品、建築物などの保存・修復技術を研究する。近年は調査機材や修復技術の進歩で、新たな発見が多い分野。
学んでおきたい教科・科目両分野とも日本史と世界史は必須だ。口伝などから研究対象にアプローチすることもあり、国語も重要。文献を読みこなす目的と、研究対象が海外という場合もあるので、英語も重要。文化財学では美術も大切。
- 地理学
-
学びの内容
自然と人間社会との関係性について研究する。気候、地形、海洋などを研究する自然地理、人口、集落、経済などを研究する人文地理、特定のエリアの自然・文化・産業などに迫る地誌学に分かれる。フィールドワーク(実地調査)も多い。
学んでおきたい教科・科目地理と歴史は日本・世界両方をよく学ぼう。そのほか、資料を読み解くための国語と英語は重要。さらに、測量をする必要がある自然地理では数学と地学をおろそかにせず、しっかり学ぼう。
- 文化学
-
学びの内容
特定の文化を取り上げて学んだり、複数の文化を比較したりしながら研究する学問。その範囲は政治・経済、社会、文学、言語、メディア、宗教、哲学と横断的で、幅広いのがこの学問の特徴で研究テーマもユニークなものが多い。
学んでおきたい教科・科目どのエリアが研究対象でも幅広い知識が必要とされる。日本史・世界史、地理、政治・経済など地理歴史、公民に力を入れよう。インタビューでのフィールドワークも多いので、国語や英語も必要。
- 外国語学
-
学びの内容
ある特定の国や地域の言語を習得し、その言語が使われているエリアに関する様々な研究を行う。文化や歴史、経済など幅広く深い知識が必要になる。在学中に専攻する言語圏の大学に1年間留学をして、単位を取得することが奨励される大学もある。
学んでおきたい教科・科目様々な外国語を身につけることになるため、高校のうちはまず英語を学ぼう。読解力、表現力を磨くほか、言語を構造的に理解するために国語も必須。研究対象への理解を深める地理歴史の知識も深めたい。
- 日本語学
-
学びの内容
普段、何気なく使っている日本語を国際的視野から見つめ、その構造を体系的に学ぶ。正確な日本語を習得し、世界に向けて日本文化を伝えるために外国語の運用能力も重視される。日本語教員を養成する大学もある。
学んでおきたい教科・科目日本語を文法、語彙(ごい)、歴史、文化などから体系的に学ぶため国語、古文、それに加えて、日本史、地理の知識が必要だ。外国語との比較研究や外国人に日本語を教えるための英語力と世界史も欠かせない。
- 言語学
-
学びの内容
言語そのものを研究対象とし、言語の理論や構造を学んだり、人間や社会と言語のかかわりを学んだりする。近年では、コンピュータによってデータを取り扱うため、言語情報処理研究などの情報処理科目を学ぶ大学もある。
学んでおきたい教科・科目言語に対する基礎的能力を高めるための国語。複数言語との比較も頻繁に行うため英語、社会とのかかわりを研究するので地理歴史も必要。データ処理能力をコンピュータで行うことも多いので数学も忘れずに。
- 法学
-
学びの内容
法律を理解し、法的思考によって、法律をどのように社会の問題解決に生かすかを研究する。「六法全書」以外にも、税法や労働法、国際法など法学で学ぶべき範囲は広い。社会の変化に伴い、法が扱う範囲はさらに広がっている。
学んでおきたい教科・科目法律の条文を読みこなし、理解する力を養う国語の力は必要だ。また、法律がつくられた背景を理解するために地理歴史と公民を学ぼう。論理的思考を養う数学も重要。各国の法律を比較する研究も盛んなので、英語も習得しておこう。
- 政治学
-
学びの内容
法律に基づいて人がよりよく生きられる社会システムを研究し、つくり上げることを学ぶ。国際政治から、市町村行政単位まで研究分野は幅広い。大量のデータ処理能力が求められたり、フィールドワークも取り入れられている。
学んでおきたい教科・科目人間社会とその成り立ちを理解するための地理歴史と公民はよく学ぼう。取り扱う問題の理解や解決法を得るため国内外の文献を読むので、国語と英語は大切。また、統計データを扱うことも多いため数学も重要。
- 経済学
-
学びの内容
個人の消費傾向から国家間の貿易まで、あらゆる経済活動を研究する。経済原論やミクロ経済学、マクロ経済学といった理論をもとに仮説を立て、数理的理論を用いて検証する。経済の変化スピードに合わせ、経済学のトレンドも変化している。
学んでおきたい教科・科目人間社会を扱うため、地理歴史や公民の勉強は大切にしよう。それらを理解するための国語、国際経済を学ぶための英語も必要だ。文系ではあるが数値などを扱って分析や理論化するための数学の素養も非常に大切。
- 経営・商学
-
学びの内容
現実社会に経済学の理論を応用する学問。企業や行政機関などの経営を研究する経営学、企業運営の状況を数値で測る会計学、取引制度や金融、証券、流通、マーケティングなどを学ぶ商学に分かれており、研究対象は幅広い。
学んでおきたい教科・科目企業と社会について広い知識が求められるので、政治・経済と、経理や会計を理解するため数学の素養は重要。経営は人を動かすために大切な国語も学ぼう。文献を読みこなすために、英語もよく学んでおこう。
- 経営情報学
-
学びの内容
比較的新しい学問で、ICT(情報通信技術)を利用した情報システムを経営に生かすことを研究する。よりよい企業経営に必要とされるソフトウェア開発、ビッグデータの活用といった情報処理の技術革新、通信技術の開発などが研究テーマとなる。
学んでおきたい教科・科目大量のデータを扱うため、数学や情報は重要。他者への説明・交渉力が求められるので、国語は大切にしよう。企業と経済を理解するため政治・経済もあわせて学ぼう。諸外国の文献を読むためにも英語はよく学ぼう。
- 社会学
-
学びの内容
人間社会における秩序に注目し、その成り立ちやメカニズム、それを取り巻く現象を研究対象とする。人間社会を取り扱うため、研究範囲は幅広い。現在進行形のテーマが多くフィールドワーク(実地調査)が重視され、現実社会に向き合う学問。
学んでおきたい教科・科目社会の仕組みと構造を理解するため地理歴史や公民をしっかり学ぼう。調査から統計資料を作成することもあり、数学も重要。また、インタビューなども行うため、国語の力は必要。文献読解のために英語の力をつけておこう。
- 社会福祉学
-
学びの内容
高齢者や障害者、乳幼児や児童などの社会的弱者を、物質的・精神的な援助によって支え、人類が幸せに共生する方法論を研究する。具体的には介護などの技術・方法論から福祉政策と、それに関する財政対策などを幅広く学ぶ。
学んでおきたい教科・科目現代社会の状況と福祉を必要としている人の現状を知るため政治・経済は不可欠だ。福祉先進国などの資料を読むための英語、コミュニケーションのための国語に加え、倫理的な問題を積極的に考えたい。
- 観光学
-
学びの内容
観光に関するあらゆる事象が研究対象となる。経済・経営・商学的な側面や、心理学、文学から観光を研究する。観光資源の発掘、観光の満足度を高める方法など、観光エリアを援助し、それらの活動に必要な分野も学ぶ。
学んでおきたい教科・科目外国人との交流や文献に触れることが多いので、英語は必須。伝える力が重要なプレゼンテーションでは国語力が問われる。観光地を深く理解するには、地理歴史も必要。事業活動を理解するのに政治・経済も大切。
- マスコミ学
-
学びの内容
不特定多数の人々に情報を伝える、マスコミとマスメディアについての本質と、その社会的影響力や果たすべき役割を学ぶ。マスメディアを中心に、他メディアとの関連性も踏まえて社会学的な視点で研究を行う。かかわる分野は幅広い。
学んでおきたい教科・科目理解力と発信力を鍛える国語、情報源として海外に当たることも多いため英語、理論的な考え方を身につける数学が必須。メディアが活躍する社会やその背景の知識も重要なため、地理歴史や公民も大切だ。
- 国際関係学
-
学びの内容
国と国との関係改善や国際紛争の解決、回避するための方法論を研究する。豊かな教養や世界各国、地域の事情や歴史的背景を理解する力、国際感覚や、国と国との架け橋になるという強い使命感と共に、広い視野が求められる。
学んでおきたい教科・科目国際関係を学ぶには、情報を得て発信するため国語と英語の習得は欠かせない。そのうえで、それぞれの問題点を理解するため地理歴史や公民、統計やデータを読み取るため、数学の知識もおろそかにできない。
- 教員養成系
-
学びの内容
小・中学校・高校の各種教員を養成する学問。教える教科・科目の専門知識や学習方法に加え、道徳や社会教育についても学ぶ。進学先の学部・学科は、どの教員免許状が取得できるかよく確認して、選択する必要がある。
学んでおきたい教科・科目どの教科も偏りなく学ぶことを大切にしたい。中学校・高校教諭ならめざす教科・科目を専門的に。実技教科・科目ならば、それぞれの実技も重要だ。共通して国語、英語を勉強しよう。
- 教育学
-
学びの内容
学校を中心に家庭や地域社会で行う教育全般についてよりよい形を模索する。教育の技術論、行政を含む教育システム、心理学など、研究対象にあらゆる角度からアプローチできるようにカリキュラムが組まれる。
学んでおきたい教科・科目公教育のシステムと現代社会を知るため、政治・経済が重要。伝える力を得るため国語と英語の語学分野の基礎的学力も必要。論理的な考え方を身につけるため数学も大切。
- その他教育学
-
学びの内容
学校以外の場での教育と指導者育成に関する研究。生涯学習における教養としての学問、文化、スポーツ、外国人に対する日本語教員養成科目などが専攻できる。専攻分野の研究と並行し、幅広い年齢や属性に対する教授法を学ぶ。
学んでおきたい教科・科目人に教えるには、言葉で伝える力を養う必要があるため、国語は大切だ。日本語教員を考えるならなおさらだ。社会の仕組みを学ぶために、公民もしっかり学びたい。英語は海外などに活躍の場を広げてくれる。
- 生活科学
-
学びの内容
家庭生活のなかでの人間関係や、生活環境を科学的なアプローチで快適にすることを追究する。衣食住をはじめとする生活の基本的な知識を学び、生活経営学では家庭のお金に関する問題を扱うなど、生活に関連することをトータルに学ぶ。
学んでおきたい教科・科目家庭科の授業は大切。また、家庭を取り巻く現象を数値を使って分析するため、数学はおろそかにできない。家事の実際を理解するため物理、化学、生物など理系の素養も大切で、国語や英語も文献読解のため重要。
- 食物・栄養学
-
学びの内容
安全や健康、栄養はもちろん、人間生活をより豊かにするためあらゆる「食」に関することを考える学問。素材の栄養素、調理・加工による変化、身体に与える影響を学ぶほか、性別や年齢など食物を食べる「人間」の条件も研究対象となる。
学んでおきたい教科・科目素材は生物、調理は物理と化学という具合に、料理に関して研究するには理科全般の知識が欠かせない。また、数値化、統計化するための数学、海外の知見を得るための英語もしっかり身につけたい。
- 被服学
-
学びの内容
繊維素材の開発・生産から被服のデザイン、縫製、販売、消費に至るまで、被服と人間のかかわりを学ぶ。被服に関する繊維や布の特性、デザイン、配色などを科学的に研究するほか、服飾美学・美術史などで、服装について文化的な側面からも研究を行う。
学んでおきたい教科・科目繊維や染色を理解するためには、化学、物理の知識が必要だ。生産や発表などは国内外で行われるため国語と英語も身につけたい。デザインも学ぶので、美術は大切。被服の歴史も学ぶため、歴史も役立つ。
- 児童学
-
学びの内容
子どもの心と体の成長について研究する。心身の成長や健全な発達、家庭を中心とした生活環境とそれをサポートする福祉などについて多角的に学ぶ。教育学、心理学、社会福祉学なども密接にかかわるので、それらの学問分野の知識も欠かせない。
学んでおきたい教科・科目言語教育の初期段階にかかわるため、国語を積極的に学ぼう。福祉について学ぶため、政治・経済の基礎知識も大切だ。幅広い成長支援のために、美術や音楽も重要だ。文献読解のために英語も身につけておきたい。
- 住居学
-
学びの内容
よりよい生活のための快適な住環境を研究する。多様な人々のための生活動線や、部屋や家具の配置による使い勝手、照明や壁紙による効果などを製図や設計の実習を含めて学ぶ。集合住宅での共同管理、隣近所と気持ちよく暮らすための生活ルールなども研究対象。
学んでおきたい教科・科目家庭科の授業は大切に。建築物を構造的に理解するため、物理の関連が深い。また、構造計算を理解する力や図面を読み取る力が必要なので数学も大切だ。海外事例も学ぶため、英語の力も磨こう。
- 美術・デザイン
-
学びの内容
視覚を中心にした芸術分野で、伝統的な絵画、彫刻、工芸に加え、印刷やWeb を前提としたグラフィックデザインやCGなども学べる。専攻内容に沿った実技・実習が中心になるが、美学や美術史といった理論的研究なども学ぶ。
学んでおきたい教科・科目いずれの専攻でも重要なデッサン力のために美術は丁寧に取り組もう。さらに、美術は自分の作品を解釈し、人に理解を求める場面も多い。言葉で表現する国語力もつけよう。活躍の場を広げるために英語力を身につけることも大切。
- 音楽
-
学びの内容
楽器、声楽を問わず音を奏で、表現するための技術論やその修得と、体系化された理論の両面から音楽を研究する。声楽を含む各種楽器の演奏技術に加え、作曲、指揮、音楽教育のほか、コンサートなどの運営を行う音楽芸術運営についても学べる。
学んでおきたい教科・科目進みたい専攻分野のレッスンを受け実技を磨くことに加えて、海外留学が盛んなので、実践的な英語を身につけたい。また、音楽学など理論も学ぶため、国語の力はおろそかにできない。
- 芸術理論
-
学びの内容
芸術家個人や作品の美のとらえ方を研究し、領域をまたがる表現・新技術による表現を研究するなど、芸術活動の発展をめざす。様々な美術作品を歴史や概論などから体系的に学び、美の果たす役割を考える。
学んでおきたい教科・科目国内外を問わず評論集や美術史などを読み込むため、国語と英語の力を身につけよう。芸術作品の背景を理解するのには地理歴史の知識が役立つ。データによる作品分析を理解するため数学の素養も大切。
- その他芸術
-
学びの内容
上記に区分されない、映画や舞台のような総合芸術、写真、文芸、書道、建築、アニメ、CG アートの理論や技術を学ぶ。特に新しいデジタルメディアなどは、この分野で研究されている。実技・実習を通して学んでいく。
学んでおきたい教科・科目分野が多岐にわたるため、進学したい分野がある大学の情報をよく調べよう。共通して大切にしたいのは美術。ほかには表現力と理解力を磨く国語と、海外作品を鑑賞したり、自分の作品を発信したりするための英語。
- 人間科学
-
学びの内容
人間そのものを研究対象とする、比較的新しい学問分野。主に心理学、社会学、教育学から成り立つが、医学や法学、生物学などの知識が求められる場合もあり、文理にとらわれない研究が行われる。また、スポーツ科学もこの一分野だ。
学んでおきたい教科・科目文理にとらわれず学ぶため、高校のうちは教科に偏りなく取り組もう。国語、地理歴史、公民はもちろん、文献や事例に触れるための英語は必要だ。生物、統計を扱うので数学の勉強も重要。
- 総合情報学
-
学びの内容
アナログ・デジタル問わず、データの収集、分析、管理、加工、活用を研究する。確率論や統計学、社会学、経済学など幅広い分野の知識を生かす。フィールドワーク(実地調査)なども行われ、現実社会の問題解決に取り組む。
学んでおきたい教科・科目情報を数値化して分析する分野なので数学は必須だ。取り扱う問題は、文理にわたり幅広いので理科、国語、地理歴史、公民はよく学んでおこう。国外の文献に当たったり、コンピュータやデータを扱ったりするため英語の力も身につけたい。
- 総合科学
-
学びの内容
現代社会の問題を、複数の学問的知識を生かして様々な角度から科学的にアプローチする学問。文系理系を問わず、従来の学問の領域を越えて取り組むため、学ぶ領域は幅広い。具体的な研究内容については各大学の学びを調べよう。
学んでおきたい教科・科目文理にとらわれず学び、問題解決に用いる手法も様々なため、高校のうちは教科に偏りなく取り組もう。文献や事例に触れるための英語は重要だ。統計を扱う数学なども重要で、苦手をつくらないようにしたい。
- 看護学
-
学びの内容
病気やけが、老いなどで弱り、衰えた人の身体や精神面をケアするための学問。看護師育成を主としているが、施設・在宅に分かれた介護、地域社会での健康・保健問題に対する地域看護など、病院以外でも必要とされる研究分野にも取り組む。
学んでおきたい教科・科目医学に関する分野なので理系全般、特に生物、化学、数学と英語の力が試される。看護師として重要な共感力と正確に物事を伝える能力を見るため、入試で小論文が出題されることもあり、国語の力も必須となる。
- 医療技術
-
学びの内容
採血や検尿などの検体に対する臨床検査とCT やMRI(磁気共鳴画像装置)などの医療機器を扱う検査分野、機能回復や社会復帰を手助けするリハビリ分野、義手や義足などを制作する補装具分野に分かれる。どの分野も最初は医学の基礎を学ぶ。
学んでおきたい教科・科目基本は生物としての人間についての学問なので、生物と化学、物理と数学の理系の力を高めなければならない。コミュニケーション力、最新情報の収集も必要なため、国語と英語の力も必要。
- 体育・健康科学
-
学びの内容
スポーツを軸に健康について考える学問分野だ。特定の競技のトップアスリートを育成するほか、その選手に対してコーチング、トレーニングを行う指導者をめざしたり、スポーツを通して広く健康増進を図る研究を行ったりする。
学んでおきたい教科・科目身体の機能や仕組みを理解するため生物、体をつくる栄養や料理を理解する化学、競技の本質を科学的に解明するため物理も学んでおくとよい。また、進みたい大学によっては体育の実技試験が行われる。
- 保健学
-
学びの内容
健康に関する社会問題の解決を考える学問。インフルエンザなどの感染症の対策に関する衛生保健学、公害などの環境を考える保健・環境学、健康と成長に欠かせない栄養や食品の安全性を研究する保健・栄養学がある。
学んでおきたい教科・科目基本は予防医学なので、医療に関連する生物、化学、英語の学力は大切だ。社会問題に関するテーマでは統計も多用するので数学。社会問題化した状況を正確に把握するための政治・経済も学んでおこう。国語も重要。
- 医学
-
学びの内容
基礎医学は解剖学、生理学、ウイルス学、免疫学などが中心だ。臨床医学は、小児科学や精神神経医学などを学ぶ内科と、消化器外科、整形外科や脳神経外科、眼科、産婦人科などを学ぶ外科に分かれる。専門の選択は卒業後となる。
学んでおきたい教科・科目人体を理解するため自然科学の基礎知識として生物、化学を重点的に学ぶ必要がある。先端医療には数学的思考も重要だ。また、最新の学術論文を理解し、研究発表を行うために英語力も必要。
- 歯学
-
学びの内容
歯や顎、舌などの機能や構造を理解する口腔(こうくう)解剖、口腔生理、口腔細菌学など歯科基礎科目を学ぶ。それと並行し口腔外科、歯科矯正、歯科放射線治療などを学ぶ歯学臨床科目がある。6年制で実習が多いことも特徴だ。
学んでおきたい教科・科目人体を理解するため、数学と生物、化学を重点的に学ぶ必要がある。また、文献や学術論文は英語で書かれたものが圧倒的に数が多いうえ、自ら研究発表する場合も多く、英語力は必須となる。
- 薬学
-
学びの内容
薬剤師、創薬研究どちらの道を選ぶにしても、薬化学、分析化学、放射化学などの基礎薬学を学ぶ。その後、製薬学、医療薬学などの応用薬学へと進む。6年制の薬学部は卒業後、薬剤師国家試験の受験資格を得られる。
学んでおきたい教科・科目大切な化学に加えて人体への影響を知るための学問なので生物にも精通する必要がある。その2科目に加えて数学の素養も欲しい。特に創薬研究に向き合いたいならば、研究活動には英語は欠かせない。
- 数学
-
学びの内容
「純粋数学」では、主に代数学・幾何学・解析学を勉強していく。コンピュータに象徴される「応用数学」は、基礎を学んだ後、これらを社会に役立てる分野である、物理、化学、生物学、統計学へ応用する方法論を学ぶ。
学んでおきたい教科・科目高校の数学は分野に偏りなく学ぼう。また、最近の数学の問題は、複数の素材から状況を解釈し、出題内容を理解する読解力も必要なので、国語も重要。応用数学を考えるなら、理科全般の勉強も大事。
- 情報科学
-
学びの内容
確率論と統計学などの応用数学から発展した。数学を基礎にプログラミング、データベース理論、アルゴリズム*理論などを学びながら、コンピュータの原理や情報の理論を体系的に理解し、理論を応用して研究を進める。
学んでおきたい教科・科目基礎中の基礎となる数学、また、プログラミングのためには英語が必要となる。情報を圧縮したり送信したりする理論を理解するためには、物理の知識も必要。
*コンピュータを動かすための規則 - 物理学
-
学びの内容
あらゆる物質現象の法則を見つけ解明していく。人が体感できるような現象を研究する巨視的立場(古典物理)と、目には見えないミクロの世界の現象を研究する、量子力学をはじめとする微視的立場(現代物理)に分類される。
学んでおきたい教科・科目物理学という名称の通り物理は必須。確率や統計、解析などで使う数学、物質自体を理解するための化学の素養も必要。研究はチームで行うことも多く、文献読解、研究発表のため国語と英語の能力も高めよう。
- 化学
-
学びの内容
物質の構造、性質、変化(反応)について実験や実習を重ね、原子・分子レベルから研究する。物質の性質を研究する物理化学、タンパク質や核酸などの生体物質や生体反応などを研究する生物化学、無機化学、有機化学、分析化学などがある。
学んでおきたい教科・科目高校で学ぶ化学は基礎中の基礎なのできちんと理解しよう。また、考え方の基礎となる数学と物理を身につけておこう。海外の文献を読み、研究発表するために国語と英語の能力も高めよう。
- 生物学
-
学びの内容
謎に満ちた「生物」をDNA、細胞という細部から、生態、行動まで幅広く研究する。分子レベルから地球規模にわたるマクロの世界まで研究範囲は幅広い。興味によって生態学、行動学、遺伝子学、生理・生化学、進化系統などが学べる。
学んでおきたい教科・科目高校の生物はしっかり学ぼう。さらにその後の研究を支えるものとして、数学と化学、物理の力も重要だ。また、文献は英語が多いので、実践的な英語に取り組んでおきたい。
- 地球科学
-
学びの内容
自然現象と呼ばれるほぼすべてと、大学によっては地球外の惑星も研究対象というダイナミックな学問。地質学、地球物理学、自然地理学のほか、天然資源開発や防災科学なども学べる。宇宙空間の研究を進めている大学もある。
学んでおきたい教科・科目幅広い分野だけに基本となる地学に加え、生物、物理、数学を勉強しておくこと。さらに世界各国で行うフィールドワーク(実地調査)に向けての英語、現地調査を促進する地理と世界史も身につけておこう。
- 総合理学
-
学びの内容
数学、物理学、化学、生物学、地球科学などの学問分野や、複数分野にまたがる研究テーマを取り扱う。何を学べるのかは大学ごとに異なるので、様々な大学の学部、学科、研究室の取り組み内容をよく調べよう。
学んでおきたい教科・科目数学と、理科の各科目、物理、化学、生物、地学はよく学んでおこう。国際レベルの共同研究が盛んな分野なので、特に実践的な英語を身につけておくと役に立つ。
- 機械工学
-
学びの内容
設計、製造、運用など機械についてあらゆることを研究・開発する。基礎となる数学や力学を学んだ後、工学に関する科目を履修する。近年では、プログラミングも重要だ。扱う機械のサイズも大きなものから目に見えない小さなものまで様々だ。
学んでおきたい教科・科目基礎となる物理、素材を知る化学、あらゆる計算に用いる数学が中心。また、生物は使用者である人間を理解することや金属以外の素材を扱うとき重宝する。プログラミングのための情報、英語も勉強しておこう。
- 電気・電子・通信工学
-
学びの内容
電気関連全般を扱う。発電と送電をメインとした「電気」、電子回路、電子部品などによる電子制御を学ぶ「電子」、インターネットなど情報通信に関する機器と運用などを研究する「通信」に分かれる。専門科目は幅広い。
学んでおきたい教科・科目電気に関する物理法則が基礎になるので物理は必須。部品をつくる素材を選ぶための化学も重要だ。情報科学とリンクする部分があるので数学や情報。また、文献は英語が多い。英語にも力を入れて取り組んでおきたい。
- 情報工学
-
学びの内容
ハードウェアの設計・生産やソフトウェアの開発研究、コンピュータの応用技術研究などを行う。かかわる分野は広く、情報科学、物理学、電気・電子・通信工学なども学ぶうえ、学部・学科によっては心理学や生物学、人間科学の知識も学ぶ。
学んでおきたい教科・科目数学に加えて、コンピュータの動力源となる電気関連の知識を理解するための物理と、素材を選ぶための化学を学ぼう。情報を扱うので情報も重要。また、文献は英文が多いので、英語力が必要だ。
- 建築・土木・環境工学
-
学びの内容
大小様々な建物に関する建築、道路や橋、堤防などインフラの土木工学、それらの建設で発生する環境問題の解決策を探る環境工学がある。それぞれ調査、設計、施工、維持管理などについての専門分野がある。
学んでおきたい教科・科目設計するには、構造力学を理解しなくてはならないので物理、鉄筋やモルタル・コンクリートなど建材の特性を知るための化学、構造計算もあるので数学も大切だ。図面を基に模型をつくるので美術や工芸も重要。
- 応用物理学
-
学びの内容
物理学の知識を応用して社会に役立つ新しい技術を開発する学問だ。陽子や中性子などの素粒子研究などが注目されている。電磁気学や量子力学などの基礎科目に加えて、物理の基礎知識を応用するために必要な科目を学ぶ。
学んでおきたい教科・科目物理と数学の学力は必須。また、実用化のため幅広い方法論を用いるので化学、生物など理系に関することは偏りなく押さえよう。研究は、複数の国の大学とチームを組むこともあるため、英語力も身につけたい。
- 応用化学
-
学びの内容
人間の生活を豊かにするために、新しい素材や物質を開発する。用途は工業、農業、薬など幅広く、再生可能エネルギーの技術開発や細菌の光合成で糖類やタンパク質をつくる技術などが注目されている。基盤となる科目は、有機化学、無機化学、物理化学、分析化学など。
学んでおきたい教科・科目化学、物理、数学の力が欲しい。また、生成する物質が人や環境へ及ぼす影響を把握するために、生物や地学の知識も必要だ。文献は英文が多いので、実践的な英語に取り組んでおきたい。
- 生物工学
-
学びの内容
生物学の知識を応用して技術開発する学問で、バイオテクノロジーとも呼ばれる。遺伝子工学、細胞工学が2 大研究分野だ。発酵作用を利用した酒やしょうゆの醸造技術も生物工学の応用といえる。医療、健康、食品など、応用分野は幅広い。
学んでおきたい教科・科目最も重要な教科は生物だが、有機化学にも関連ある分野なので化学、実験を行うために必要な物理も学んでおこう。文献は英文が多いので、英語も重要。また、遺伝子関連では数学の知識も必要となる。
- 金属・材料工学
-
学びの内容
天然の原料から新しい性質や機能を持った材料を開発する。つくり出す方法、過程、特性の研究。また、完成後の材料の加工方法や機能なども研究対象だ。環境への配慮が材料にも求められるなど、社会の要請にこたえる学問だ。
学んでおきたい教科・科目基本となるのは化学なのでしっかり勉強しておこう。実験に必要となる物理と数学、生物由来の素材を研究したいなら、生物の勉強も欠かせない。海外の文献を読むための英語力も身につけておきたい。
- 資源・エネルギー工学
-
学びの内容
地下や海底の鉱物、化石燃料の探査・採掘などを研究する資源工学と、エネルギーを採り出し、輸送や貯蔵、燃焼効率改善などを研究するエネルギー工学に分かれる。地熱発電、太陽エネルギー利用に加えて環境への配慮も求められる。
学んでおきたい教科・科目この分野では、地質をはじめ地球について理解するための地学と、研究対象となる資源を理解するための化学はよく学んでおきたい。そのほか、研究や実験で使う数学、物理、英語の勉強も必要。
- 航空・宇宙工学
-
学びの内容
航空機、ロケット、人工衛星などの設計から製造、運用までに関する研究を行う。大気圏内の飛行における省力化や安全性、宇宙空間における人工衛星や宇宙ステーションの耐久性、移動方法、人間の活動なども研究の対象だ。
学んでおきたい教科・科目軌道計算などに使われる数学、重力や流体力学などの理解につながる物理、機体の材料にかかわる化学は重要。研究は大人数かつ国際的に行われることが多いので、国語と英語のコミュニケーション能力を高めよう。
- 船舶・海洋工学
-
学びの内容
船舶・海洋工学は船舶と石油プラットフォームに代表される海上構造物の製造や運用に関する研究を行うほか、海底や海中にあるスペース、水産物・鉱物・エネルギーといった資源の有効活用と環境保全を考える。
学んでおきたい教科・科目海洋を対象にするので地学は重要。また、水や抵抗に関する特性を理解するための物理と数学も欠かせない。船の建造や資源の活用なら化学の素養も必要だ。国内外にまたがる分野なので英語も勉強しよう。
- 商船学
-
学びの内容
船・海・海上輸送の3 つの分野で船を運航する航海学、船のエンジンや制御にかかわる機関学など、「船の運航や開運」に焦点を当てた研究を行う。多くの大学では数か月の乗船実習を設けているが、船員の養成を目的としない学科もある。
学んでおきたい教科・科目外国とのコミュニケーションを想定して、英語の海運用語を大学でも学ぶが、実用的な英語の力はしっかり身につけておきたい。物理と数学のほか、気象や海に関する知識、海洋環境の生物についても知っておくとよい。
- 経営工学
-
学びの内容
経済学と工学が組み合わされた学問だ。研究対象は、企業や工場の生産部門、会社経営全般、自治体、国際組織の運営など多岐にわたる。かかわる分野は経済学、心理学、数学、物理学やプログラミングなど幅広い。
学んでおきたい教科・科目政治・経済のほか、統計やデータ管理のための数学と物理、つくり出す製品の原料を知る化学などが必要になる。円滑なコミュニケーションを図るのに大切な国語と英語の力も必須だ。
- 工業デザイン
-
学びの内容
あらゆる工業製品の最終的な形を決める、機能性と デザイン性の両立をめざす学問だ。使いやすさや安全性のほか、製品 によっては消費者へのアピール性やユニバーサルデザイン*の取り 入れ方、環境対応などの多様な要求がある。
学んでおきたい教科・科目製品の機能性を熟知するためには物理と数学を学ぶ必要がある。製品の原材料を理解するための化学の力もつけておきたい。多くの事例に触れる可能性を広げるための英語や、感性を磨くための美術も重要。
*すべての人が快適に利用できる設計
- 農学
-
学びの内容
安全でおいしい作物を効率よく育てることを目的として、遺伝、育種、栽培、作物、土壌、バイオテクノロジーや生態系、マーケティング、気象など農業にかかわる分野を幅広く学ぶ。実験や農場でのフィールドワーク(実地調査)も重要。
学んでおきたい教科・科目育てる品種や害虫・害獣のことを学ぶために生物、土壌や農薬について理解するための化学も必要だ。2つの教科を支える土台となる数学も忘れずに。文献の理解や、海外での実習に備えて英語も学ぼう。
- 森林科学
-
学びの内容
植生、そこにすむ動物、林業や狩猟といった森林を生活の一部とする人たちなど、森林にかかわるものすべてを研究対象としている。森林の保護と永続的な活用を目的とし、生物学的視点や経済・経営学的視点を持って研究する。
学んでおきたい教科・科目地形に関する地学は重要だ。それに加え、生態系を知るための生物、土壌や肥料の知識を得るための化学の素養も必要となる。また、理系の基礎となる数学と物理、文献を読みこなす英語も勉強しておこう。
- 農芸化学
-
学びの内容
具体的には、土壌改良や防虫などに使われる農薬や肥料の開発、食品の加工・保存、食品の栄養学的な解明などに取り組む。環境保全を目的とした生分解性プラスチックなどの研究も行われるなど、生かされる分野は広い。
学んでおきたい教科・科目高校の生物はよく理解しておこう。農薬をつくるには化学の知識が重要。文献理解はもちろん、国際的に行われる共同研究もあるので、英語も大切。コンピュータを使った解析もあるので、数学、情報も積極的に学ぼう。
- 農業工学
-
学びの内容
農業地域の環境を整備することによって、農産物を効率よく生産するための技術開発や研究を行う。水資源を利用する設備を整える農業土木や、緑化推進のためのスプリンクラーなどの農機具を設計、製造する農業機械の研究分野がある。
学んでおきたい教科・科目土木を学ぶ基礎になる物理と数学を勉強しておこう。農薬系を知るための化学と作物や周辺の生物に対する知識も必要なので、生物も重要。大規模農業は本場の海外で学ぶことも多いので英語力もつけておきたい。
- 農業経済学
-
学びの内容
同じ野菜でもブランド力があればよく売れ、付加価 値があれば高く売れる。そのような経済学の知識を利用して、農業界 の経済問題を解決する。地方活性化で話題となる「第1次産業」から 「第6次産業*」への転換がそれに当たる。
学んでおきたい教科・科目作物、土壌、水、気候、農薬、遺伝子など幅広い知識が求められるので、高校の生物、化学を中心に、物理や数学も大切にしよう。また、経済分野に通じる必要があるので、政治・経済と英語もよく勉強しておこう。
*農林漁業生産(第1 次産業)と加工(第2 次産業)、販売(第3 次産業)の一体化 - 水産学
-
学びの内容
主に生物資源の捕獲手段にかかわる漁業学、養殖などにかかわる増養殖学、流通や加工・保存法に関する食品生産学の3分野だ。近年、海洋資源を守りながら、人の生活を豊かにする方法を考える実習が重視される。
学んでおきたい教科・科目生物資源を対象とするので生物は学んでおきたい。加工や保存を理解するには化学が有効。漁業者だけではなく研究者も海外の洋上に出ることがあるので、コミュニケーション能力を高める国語と英語も大切。
- 獣医学
-
学びの内容
獣医師を養成することを目的としている学問分野。6年制で、卒業すれば獣医師の国家試験受験資格が得られる。家畜やペットとなる動物の治療法を学び、ウイルスや寄生虫など感染症の予防対策なども研究する。
学んでおきたい教科・科目動物の治療なので、生物の勉強は必ずしておこう。治療や感染症の防疫では薬も使用するので化学の知識が役に立つ。論理的思考を磨く数学や、多くの最新論文に触れるためには英語も欠かせない。
- 畜産学
-
学びの内容
畜産に関する全般を扱う。研究分野は「飼育」「飼料」「解体・加工」「経営」「環境問題」「社会との共生」など多岐にわたる。人間にとって有用な動物の利用という側面から、ペットが飼い主に与える癒い やし効果などを研究する場合も。
学んでおきたい教科・科目最も勉強すべきは生物。飼料に混ぜる薬品なども扱うので化学と数学の素養も身につけよう。また、英語論文の読み書きが多い分野なので英語は必要。動物の命にかかわることなので、倫理も学んでおこう。