追手門学院大学/法学部の詳細情報
学科・定員・所在地
学科・定員
法律学科(230名)
所在地
1~4年:大阪
※変更の場合もありますので、学校が発行している資料やホームページにてご確認ください。
法学部の偏差値を見るプロフィール
●令和の市民視点で法律を考える、新しいスタイルの法学を展開
●グループ学習をはじめ、学生参加型の主体的な学びを展開
●ジェンダーや国際関係、企業法務など、現代のニーズに応える課題を扱う
養成する具体的な人材像に対応した「政策法務」「企業法務」の2コースを設置。1年次からの主体的な学びでつちかった視点・関心を、めざす人材像に合ったコースに分かれて、さらに展開、探求します。
【学生数】
464人(2024年5月1日現在)
【専任教員数】
20人(2024年5月1日現在)
法律学科
【講義・学問分野】
刑事手続法I、比較法、法学入門、国際関係法I、行政法I、商法I、法と政治、法と心理、ジェンダーと法、社会保障法、国際取引法 など
学部の特色

令和の市民視点で法律を考える、新しいスタイルの法学を展開

法に関する専門知識および法知識の基礎となる基本事項や思考方法といった法的素養とともに、幅広く深い教養、主体的な判断力や豊かな人間性を身に付けます。それらを社会のさまざまな場面に適用できる応用力をもって、社会のさまざまな分野で日常的に生じる法的な業務や諸問題を的確に処理することのできる職業人を育成します。
グループ学習をはじめ、学生参加型の主体的な学びを展開
1年次から少人数のゼミ形式の授業を展開。従来の大講義形式だけでなくグループ学習を取り入れ、学生同士が語り合い討論する主体的な学びを重視しています。
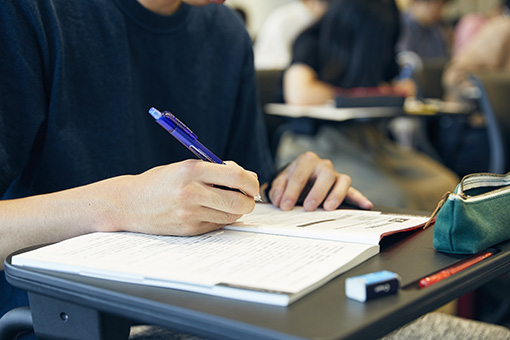
ジェンダーや国際関係、企業法務など、現代のニーズに応える課題を扱う
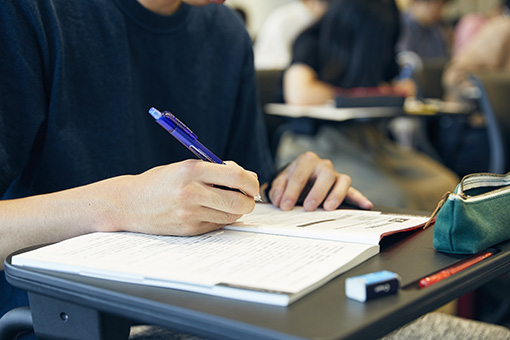
主に法律家をめざすこれまでの法学部とは一線を画す、市民目線の法学部です。オーソドックスな従来のカリキュラムは残しつつ、抽象的な法律の項目だけを学ぶのではなく、個人にとって身近で誰にとっても大切なテーマや、現代社会のニーズに沿った課題も積極的に扱っていきます。
[科目例]
・行政倫理と自治体法務:自治体の役割と未来を考える
・企業倫理と企業法務:企業のあり方と未来を考える
・国際取引法:国際的な商取引の仕組みを知る
・ジェンダーと法:ジェンダーの視点を明らかにする
・科学技術と法:先端技術への法の対応を考える
この学部のことを詳しくチェック
学べること
法律学科
社会のさまざまな分野で日常的に生じる法的な業務や諸問題を的確に処理できる人材へ
●政策法務コース
主として、国家公務員(総合職・一般職)・地方上級公務員やNPOなどの政策法務を目指すコースです。行政法、地方自治法などの知識をもとに、行政実務に携わり、政策立案(産業推進、都市計画、雇用対策、福祉充実など)ができる力を養成します。
●企業法務コース
主として、民間企業へ就職し企業法務を目指すコースです。民法・商法に加え、経済法や労働法などの法的知識も活かし、商取引関係や労務関係などの企業活動における法律事務の処理や法律問題(M&A、訴訟対策、企業再生など)に対応する力を養成します。
【授業・講義】
知的財産法
知的財産法に関する基礎的な知識の修得をめざし、知的財産法を構成する特許法、著作権法、意匠法、商標法などについて理解します。身近に実際に生じる知的財産法に関する基本的な問題を実践的に解決できる能力を養います。
アドミッションポリシー
入学者受け入れ方針
法学部では、組織として研究対象とする中心的な学問分野を「法学分野」として、法学分野に関する教育研究を通して、「法律に関する基礎的・基本的な知識と技能の習得のもと、法律の理論や手法を活用し、法律に関する諸活動を主体的・合理的に行うことのできる能力と態度を育成する」ことを教育研究上の目的としています。
また、法学部では、「幅広く深い教養及び主体的な判断力と豊かな人間性を身に付け、法に関する専門知識及び法知識の基礎となる基本事項並びに思考方法といった法的素養を有して、それらを社会の様々な場面に適用できる応用力をもって、社会の様々な分野で日常的に生じる法的な業務や諸問題を的確に処理することのできる職業人」を養成するための教育課程の編成としています。
この法学部における教育研究上の目的や養成する人材と教育課程との関連性を踏まえて、入学者選抜の基本的な受入れ方針は、法律や法律の諸活動に対する興味と関心及び学部教育に対する学習意欲を有しており、学部教育を受けるに相応しい基礎学力と適性能力を有している者を受け入れることとします。
法学部の具体的な入学者受入れの方針は、以下の通りとします。
(1)法律と法律の諸活動に対する興味や関心と学部教育に対する学習意欲を有している。
(2)高等学校で履修した主要科目について、教科書レベルの基本的な知識を有している。
(3)物事を正しく認識し、自分の考えを適切に表現し、他者に対して的確に伝えられる。



