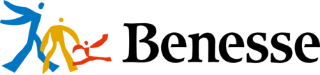教科と学問から考える
文理選択
高校で学習する主な教科・科目について、特にかかわりの深い学問を紹介する。
次の「学問系統辞典17」もよく読んでみよう。
- 国語
-
近い学問系統文学/語学
文学は国内外の文学作品など、語学は言語そのものを研究する学問なので、高校で学ぶ国語の学習内容と直結している。
学問につながるこの教科の力古典から現代文まで幅広く扱うため、語彙はもちろん、様々な表現や文法の知識、読解力などが文学・語学ともに必要になる。また、国語を学習する中で出合った文章や書物も文学・語学の興味のきっかけになる。
- 英語(外国語)
-
近い学問系統文学/語学/国際関係学
英語は国際的に広く使われている言語であり、どの学問ともかかわる。特に関係が深いといえるのが、上の3つの学問系統だ。英語以外の外国語も含まれる。
学問につながるこの教科の力英語の4技能である「聞く」「読む」「話す」「書く」は、英語そのものを学ぶ場合はもちろん、英語を使う多くの学問でも重要だ。加えて、今やどの学問領域でも、研究資料を理解するために、英語を使いこなす力が必要だ。
- 地理
-
近い学問系統文学/社会学/国際関係学
地形や国の産業などを学ぶ地理は、現代社会の問題を考えるうえで重要な科目。社会学系統や国際関係学系統と関係が深い。
学問につながるこの教科の力人々が暮らす社会やその文化は、住んでいる場所、気候などに強く影響を受けている。そうした地理的な知識は、社会や国際関係を理解するうえで欠かせないものだ。また、他の国の文化などを理解することにもつながる。
- 歴史
-
近い学問系統文学/社会学/国際関係学
国や地域、人類の歴史は、歴史を学ぶ学問系統だけでなく、現代社会を研究する学問とも深く結びついている。
学問につながるこの教科の力基本的な歴史の知識は、現代社会の成り立ち、あるいは国や地域の関係などの深い理解につながる。また、歴史を学ぶことによって身につく「自分が歴史をつくる一員」という自覚は、これからよりよい社会をめざして学ぶ原動力になる。
- 現代社会、政治・経済
-
近い学問系統法学/経済・経営・商学/社会学/国際関係学
現代社会に関して直接学ぶ科目のため、いずれも現代社会や人間の社会的な活動を学ぶ学問の多くと関係している。
学問につながるこの教科の力現代社会の仕組み、政治や経済は、複雑なシステムで成り立っている。半面、様々な問題もある。高校で身につけた知識を用いて、そうした問題を考察する力が、大学で専門的に学問に取り組むときに役立つ。
- 倫理
-
近い学問系統文学/法学/社会学
人間がどう生きるかを学ぶので、同様に人間の生き方を考える文学や社会学、社会のルール、「法」を学ぶ法学と関係が深い。
学問につながるこの教科の力倫理で学ぶ考えは、大学で思索を発展させていく土台となる。現代社会の倫理的課題も学ぶため、大学で何を学ぶべきか、考える材料にもなる。また、学びの中で培われる論理的思考力もほかの学問を学ぶうえで大きな武器になる。
- 家庭
-
近い学問系統生活科学/科学/看護・保健学
家庭科は身の回りの生活のことを学ぶので、関係がある学問も、日常生活に極めて近い実践的な学問が多い。
学問につながるこの教科の力家庭で学ぶ調理、栄養、服飾などの各分野はいずれも生活にかかわるため、生活科学に欠かせない基礎知識になる。一方、栄養や子どもに関する知識や技能は看護・保健学といった学びにも深くかかわる。
- 音楽
-
近い学問系統芸術学
芸術の一領域である音楽は、芸術学系統と関係が深い。一方、人間の生活に深く根づいているので、総合科学にもかかわる。
学問につながるこの教科の力音楽の鑑賞、歌うこと、楽器の演奏などは、いずれも芸術学につながる。学校教育(幼・小)の教員をめざす場合も重要だ。また、音楽の理論的な知識は、総合科学で人間の精神・身体研究などに役立つこともある。
- 美術
-
近い学問系統芸術学
音楽と同じく、芸術学系統の絵画や彫刻などを扱う分野と関係が深い。また、総合科学にかかわることもある。
学問につながるこの教科の力美術を鑑賞し、自他の感性を引き出したり、自分で絵画や彫刻などの方法を通して表現したりすることが、美術で学ぶ2つの大きな柱。得意な表現方法だけでなく、美術に対する解釈などの思考方法も身につけておこう。
- 保健体育
-
近い学問系統看護・保健学/医学(歯学)/総合化学
実際に体を動かしたり、健康について学ぶ保健体育は、人間の体にかかわる学問と密接につながっている。
学問につながるこの教科の力保健で学ぶ人体に関する知識などは、健康について学ぶ際の助けになる。一方、スポーツに親しみ、心身の健康を図る体育は、効果の高い運動方法や、体の適切な動かし方を研究する場合に役立つだろう。
- 物理
-
近い学問系統理学/工学
自然現象を物理学的に研究する理学系統の物理は、実社会への応用を考える工学系統ともかかわりが深い。
学問につながるこの教科の力実験や観察を通して身につける物理学的な探究方法や、エネルギーなどへの理解・興味は、理学や工学を学ぶうえで必須の基本的な力だ。仮説を立てたり、考察したりする習慣を身につけよう。
- 化学
-
近い学問系統理学/薬学/農・水産学
物質を対象とする理学系統の化学、薬を扱う薬学、物質の生物への応用などを研究する農・水産学系統などに直結する。
学問につながるこの教科の力自然現象における物質の働き、反応などを、実験・観察などを通して探究することが、大学で化学系の学問を学ぶうえでも大切になる。新しい物質をつくり出し、実社会で応用することまで研究する際に必要だ。
- 生物
-
近い学問系統理学/農・水産学/看護・保健学/医学
理学系統の生物学や、生物の利用や仕組みについて研究する農・水産学、看護・保健学、医学(歯学)とのかかわりが深い。
学問につながるこの教科の力身の回りの生物を題材に学んで得られる、生物の多様性や共通性、遺伝子、生物同士のつながりなどの知識は、大学での学びの土台となる。また、高校で習う生物の観察などの基本的な手法も、大いに役立つ。
- 地学
-
近い学問系統理学/工学
地球や天文について学ぶ理学系統や、工学系統とかかわりが深いが、研究対象のスケールが大きいため、かかわる学問も実際は幅広い。
学問につながるこの教科の力野外などで実際に観察して、地学的な情報を得ることは、大学でのフィールドワーク(実地調査)につながっていく。また、非常に長いスパンによる時間的変化、空間的な広がりで物事をとらえる力は大学でも生かされるだろう。
- 数学
-
近い学問系統理学/工学/経済・経営・商学
数学は理系のみならず、文系でも非常に重要だ。理学・工学系統のほか、数字を使って研究する経済・経営・商学とも関係が深い。
学問につながるこの教科の力数学Ⅰで身につく数学的・論理的な考え方は、学問の土台になる。数学Ⅱ、Ⅲ、A、Bは、進路に応じて必要なものを選ぶが、いずれも大学での数学の基礎。また、統計の知識などは、文系の学問でも必要になることも多い。
- 情報
-
近い学問系統理学/工学/総合科学
情報社会における情報の理解、その正しい利用は、コンピュータなどを扱う学問系統や、情報の利用を前提とした研究分野とかかわる。
学問につながるこの教科の力ICTや情報の技術的背景を知ることは、それを利用して新しい価値をつくり出すときのベースになる。特に関係の深い工学などの分野では、情報セキュリティー、ネットワークの仕組みなど、幅広い知識・技術が生かされる。
- HOME
- 自分を知る
- 文理選択と将来
- MENU