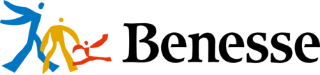学問系統辞典17
すべての学問系統に目を通し、「これが自分の興味に近そう」と思った系統の分野を見ていこう。
- 01文学系統
-
文化、文学から歴史までヒトの歩みを探る
人類が残してきたことやものを研究し、人間という存在を理解すること。 また、未来への道しるべを探るための学問だ。研究範囲は、文学作品や歴史書、宗教書、建造物から、積み重ねられてきた文化・風習、行動の傾向など幅広い。 対象は人類全体から、特定の作家や歴史的人物まで様々だ。過去の人々が残したものを手がかりに、人間の行動や社会とのかかわりを研究する。
分野- 1.日本文学
- 2.外国文学
- 3.哲学・倫理・宗教
- 4.心理学
- 5.歴史学
- 6.考古学・文化財学
- 7.地理学
- 8.文化学
- 02語学系統
-
言葉はコミュニケーションツール、と割りきれない奥深さ
普段、私たちが使っている「言葉」を科学的に研究・解明する語学系統。何千種類もあるといわれる言語だが、そもそも言語とは何か、その歴史や言葉の構造や仕組み、文法、発音・発声を科学する言語学、特定の言語を選んで習得し、異文化理解を深める外国語学、日本語を国際的視野からとらえ直す日本語学などに大別できる。言葉そのものの謎を解き明かす楽しみがあり、使える言語が増えれば、自分の世界も広がる学問だ。
分野- 9.外国語学
- 10.日本語学
- 11.言語学
- 03法学系統
-
近代国家の基礎中の基礎「法」を学び社会を豊かに
近代国家とその国民が努力により勝ち得た法治の概念を、先人が重ねた歴史とともに知り、現在と未来をよりよくするための学問だ。近代国家に生きる人々が幸せに暮らすためのルールづくりとルールの理解、ルールの正しい運用を研究する。ある問題に対し、法学は法律と法的思考にのっとった解決方法を学び、政治学は政策や行政といったシステムを用いた解決方法を学ぶ。想定外の新たな問題に対しては、両者が協力し新たな提案をすることもある。
分野- 12.法学
- 13.政治学
- 04経済・経営・商学系統
-
社会における経済活動の基礎理論と実践理論を研究・構築
現在の主流は資本主義の貨幣経済における個人や組織の行動の研究だ。特定の経済活動に関連するすべての人や団体(主に会社組織だが、行政機関も含まれる)それぞれの関係性や望むものを把握し、結果を予測すること。第三者的視点で経済の流れを見極め、予測する経済学、営利活動をする立場でより大きな利益を得るための方法論を考える経営・商学、経営における ICTの積極的な活用法を研究する経営情報学の3つに分類される。
分野- 14.経済学
- 15.経営・商学
- 16.経営情報学
- 05社会学系統
-
社会の森羅万象を多角的に解明する
人間と社会が織りなすすべてを研究する学問。その対象は、個人の、社会との向き合い方から、社会システムへの問題提起や解決策の提示までと幅広い。 主に社会現象を対象に人と社会の相互作用について研究する社会学、公的な社会福祉のあり方について学ぶ社会福祉学、営利的な施設の運営から観光を通した地域のあり方までを探る観光学、マスメディアが社会に果たす役割を探求するマスコミ学の4分野を含む。
分野- 17.社会学
- 18.社会福祉学
- 19.観光学
- 20.マスコミ学
- 06国際関係学系統
-
国と国との利害関係を熟知し、最適な解決策を探る
国と国との関係性について理解し、平和な関係を築くための方法を探す。戦争や貧困に加え、報道が増えている人種間闘争、移民・難民などテーマは様々だ。その要因を探るだけでも、対立する当事国の国民(民族)性と文化、歴史、地理など、把握しなければならない要素が多く、知的探求心が刺激される。どの課題も複雑ですぐに解決・改善に至らない可能性が高いが、社会に問題の理解を促進する存在として必要とされる。
分野- 21.国際関係学
- 07教員養成・教育学系統
-
「教育」の本質を考え、学びの場で実践する
児童、生徒一人ひとりの心身の成長のために、体系的に研究された教育方法を応用し、様々な学びの開発・提供の研究がされている。
教育のあり方を探る教育学、幼稚園、小・中学校、高校の教員を養成する教員養成系分野、学校教員以外の指導者をめざして専門教育を受けるその他教育学の3つの学問分野が含まれる。教育学では教育を取り巻く諸問題を分析することに重点を置き、教員養成系では実践的に取り上げる。分野- 22.教員養成系
- 23.教育学
- 24.その他教育学
- 08生活科学系統
-
あらゆる生活シーンでの「快適」を科学する
基盤となる衣食住や家庭環境をメインに、生活するあらゆる場面での快適を研究し生活向上を目標とする。消費者視点で問題を発見し、企業や行政に指摘する役割も持つ。衣食住の3分野は最も生活に密着しているため、それぞれ被服学、食物・栄養学、住居学として学ぶことができる。児童の心身の発達や健康を科学する児童学。そのほかの生活するうえで必要な家計、家庭内や居住地域周辺での人間関係などは生活科学の研究対象だ。
分野- 25.生活科学
- 26.食物・栄養学
- 27.被服学
- 28.児童学
- 29.住居学
- 09芸術学系統
-
正解はない「表現」を追求し、芸術そのものを学ぶ
多種多様な芸術の歴史や意味を研究する学術論や技術論など、あらゆる角度から芸術を研究したり、自らが取り組んで、表現力を磨く。
視覚的芸術を扱う美術、聴覚的芸術を扱う音楽、どちらも扱う映画や舞台などの総合芸術が基本となり、工芸、放送、映像、演劇、文芸、写真、建築など幅広い表現手法を学べる。表現者としてだけでなく、評論家や研究者、キュレーター、芸術界を動かすプロデューサーをめざす勉強もできる。分野- 30.美術・デザイン
- 31.音楽
- 32.芸術理論
- 33.その他芸術
- 10総合科学系統
-
複雑化した現代社会を多角的に研究する
問題解決に必要な専門知識を総合的に学ぶ、比較的新しい学問分野。例えば、海の水質汚染問題を解決するには、海を管轄する行政を動かす政治学、経済・経営学など文系の知識と、海水を浄化する理系の知識が必要だ。このように文系と理系両面からアプローチして問題の解決策を探る学問。人間を分析する人間科学、現代社会の問題を科学的に研究する総合科学、それらの問題を情報という角度から解決策を探る総合情報科学に大別される
分野- 34.人間科学
- 35.総合情報学
- 36.総合科学
- 11看護・保健学系統
-
患者の回復をサポートする看護と、人々の健やかさを保つ保健
医療技術の進歩に伴う看護技術の高度化に対応する人材育成と、高齢化への対処や、病気の予防など現代社会の健康問題を研究する。
大きく4分野に分かれており、看護師をめざす看護学、リハビリや臨床検査など医療行為のサポート分野を学ぶ医療技術、スポーツを中心に健康増進を目的とする体育・健康科学、生活習慣病を減らす対策や伝染病の拡大を防ぐ予防医学を研究する保健学がある。分野- 37.看護学
- 38.医療技術
- 39.体育・健康科学
- 40.保健学
- 12医学系統
-
頭から爪先まで人体と病の仕組みを理解する
個体や器官から細胞分子レベルまで、人間の身体についての研究を基礎に、病気の治療や予防に関する研究をする。基本は病気やけがの治療を施す医師を養成するための学問だ。iPS細胞や免疫などを利用した最新医療研究が活発化するなど、研究医も注目されている。
人体や精神が研究範囲だ。医学部を卒業することで医師国家試験の受験資格を得られ、試験に合格すると医師免許証が取得できる。分野- 41.医学
- 13歯学系統
-
歯と口腔内の健康と機能を整える
口の中の健康と機能を維持するための学問だ。歯学といっても扱う範囲は幅広く、口の中からノドまでを含む口腔内、顎の関節まで含んでいる。
歯学の役割は大きく分けて2つあり、患部を治療し正常な機能を回復させることと、80歳まで自分の歯を20本残そうという「8020運動」に代表される予防医学だ。歯学部は卒業することで歯科医師国家試験の受験資格を得られ、試験に合格すると歯科医師免許証が取得できる。分野- 42.歯学
- 14薬学系統
-
個別化とジェネリックで転換期を迎える分野
薬物にかかわる学問で、薬剤師を養成する医療薬学と新薬開発を行う医薬品化学に大別される。物質の構造や変化の仕組みを理解する化学分野と、それが人体に与える影響を研究する生物学的分野から成る。
現在、医療分野とDNA解析の進歩によって、人間という種に対する効果を得る薬から、個人の人体特性に合わせた“個別化”という方向への転換期を迎えているので、新たな発見に立ち合う可能性もある。分野- 43.薬学
- 15理学系統
-
古代から脈々と続く自然界の理を知る学問
熱いお茶はいずれ冷める。その当たり前の「冷める」という現象をどう理解するか、など理学の分野では、自然界で起こる様々な事象を解明し、法則を導き出す。
数学や、それを発展させコンピュータに応用させる情報科学、現象の本質に迫る物理学、物質とその変化を知る化学、生命を科学する生物学、地球と宇宙が対象の地球科学、複数の手法と知識を用いる総合理学がある。分野- 44.数学
- 45.情報科学
- 46.物理学
- 47.化学
- 48.生物学
- 49.地球科学
- 50.総合理学
- 16工学系統
-
原理や法則を応用して新しい技術を創出
数学と自然科学で解き明かされた原理や法則を使って、現実世界の様々な問題を解決するのが工学系統だ。幅広い学問領域にかかわり、「こんなことができたらいいのに」を形にする学問といえる。
機械工学、金属・材料工学、電気・電子・通信工学、情報工学などに分かれている。近年の研究の場では、それぞれの研究用にカスタマイズできるプログラミングの知識・技能が必要とされる場面も多い。分野- 51.機械工学
- 52.電気・電子・通信工学
- 53.情報工学
- 54.建築・土木・環境工学
- 55.応用物理学
- 56.応用化学
- 57.生物工学
- 58.金属・材料工学
- 59.資源・エネルギー工学
- 60.航空・宇宙工学
- 61.船舶・海洋工学
- 62.商船学
- 63.経営工学
- 64.工業デザイン
- 17農・水産学系統
-
農・畜・林・漁の技術を修得、応用、発展を促す
第1次産業に関連する学問。自然を相手に問題解決に取り組む。
農を取り巻く全般を扱う農学、工学の手法を使って生産技術を高め、農環境を整備する農業工学、化学の知識を生かして食物の可能性を広げる農芸化学、消費活動として農業をとらえる農業経済学などが学べる。農業は規模が大きいため細分化されているが、森林科学、畜産学、水産学でも周辺研究を行っている。獣医師を養成するための獣医学もこの系統に入る。分野- 65.農学
- 66.森林科学
- 67.農芸化学
- 68.農業工学
- 69.農業経済学
- 70.水産学
- 71.獣医学
- 72.畜産学
- HOME
- 自分を知る
- 文理選択と将来
- MENU