社会学を学んでいる先生のインタビュー

プロフィール
菊地淑人先生
生命環境学部 地域社会システム学科
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程修了。国立文化財機構奈良文化財研究所を経て、2016年より現職。
動画でチェック!
この学問の面白さとは?
文化や歴史を生かした魅力的な地域づくり
先生の探究ヒストリー
夢中になったきっかけ
遺跡から見えてきたこと
古代史が好きだった私は、大学で考古学を専攻し、古墳時代の遺跡について研究しました。やがて遺跡から「今」に思いをはせるようになり、「遺跡や遺物などの文化財は、今を生きる人々とどうつながるべきなのだろう」と疑問に思いました。そこで大学院では、「文化財保護に関する理論や政策」について学び、地域に残る文化的景観の調査を行いました。
現在の研究内容
よりよい地域づくりのために
皆さんは、自分が住んでいる地域に、どのような歴史や文化財があるか知っていますか。例えば山梨県はぶどうやワインが有名ですが、どのようにして人々に知られるようになったのでしょうか。
私は、歴史や文化資源を生かした地域づくりや観光地づくりについて研究しています。実際に地域に出て歴史や文化を調査すると、今まで気づかなかった「地域らしさ」が見えてきます。フィールドから得た知見を地域づくりの「理論」と結びつけることで、持続可能で魅力的な地域づくりに貢献できたらと願っています。
高校生へのメッセージ
地域らしさを肌で感じよう!
社会学系統は、社会に存在するさまざまな現象について研究する学問です。例えば観光をテーマに地域で調査を行うと、自然や歴史、生活、生業*など、地域らしさを立体的に理解できます。ぜひ積極的に外に出て、皆さん自身の目で地域の魅力を感じ取ってください。
*生活のための職業
先生の探究STORY
学問に目覚めたきっかけ
中学生時代、家族旅行で奈良・京都を訪問し、飛鳥地方の遺跡に興味を抱くように。高校の授業で亀石という古代の石造物について調べ、論文にまとめる。
大学時代

考古学を専攻、遺跡の発掘調査に参加。炎天下、刷毛で土器を慎重に発掘するのは大変だが、同時に「遺跡に近い場所にいる!」と実感。
現代とのつながりターニングポイント
考古学の研究に取り組みながら、「文化財は“今を生きる人たち”とどうつながるべきなのだろうか」と疑問を抱く。
学問の魅力を感じられる
先生オススメの1冊
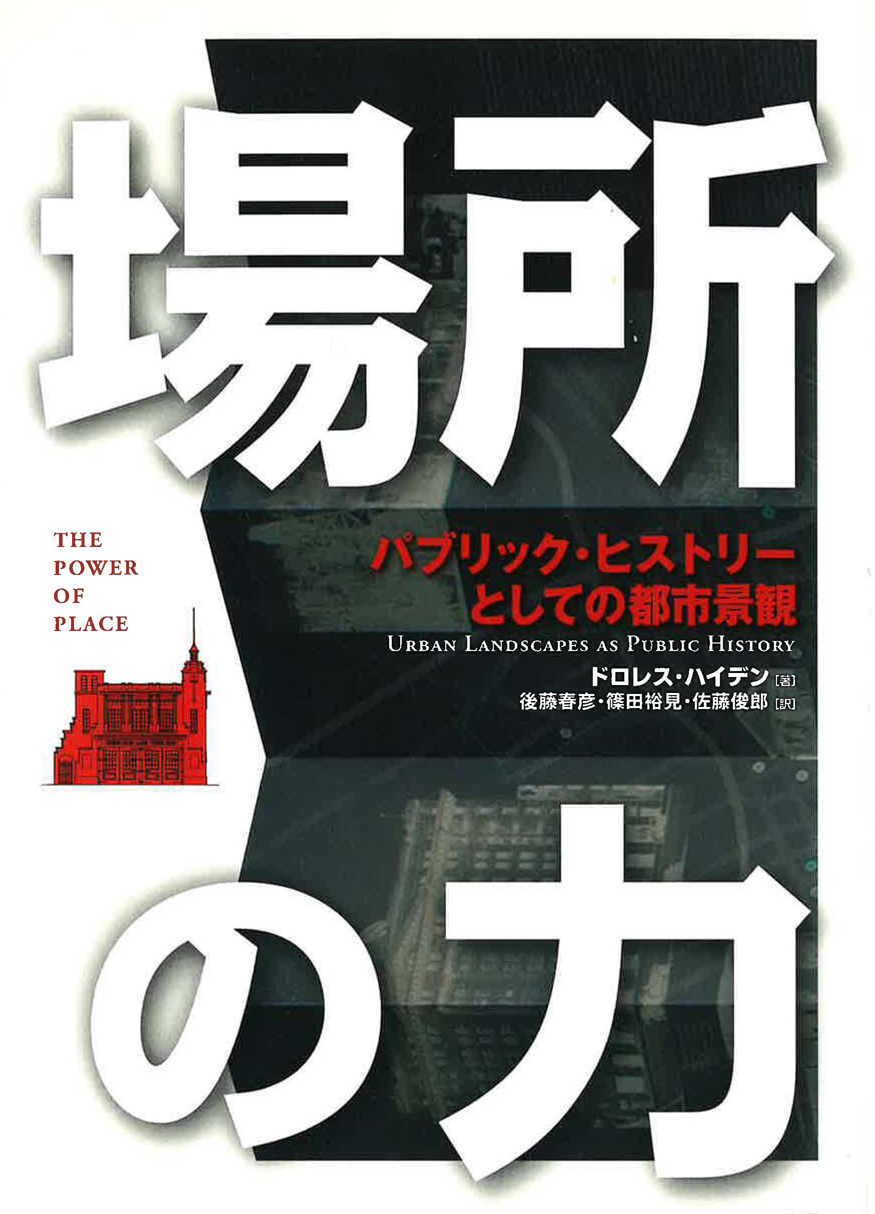
『場所の力—パブリック・ヒストリーとしての都市景観』
学芸出版社
ドロレス ハイデン/著
先生の探究ヒストリーをチェックしてみよう
-

歌舞伎役者の日記から江戸時代の大衆演劇を分析!
ビュールク・トーヴェ先生
埼玉大学 大学院 人文社会科学研究科
-

生まれ育った地域の「方言」を解き明かす!
高木千恵先生
大阪大学 大学院 人文学研究科
-

人の権利のあり方を憲法の視点から考える
石川 裕一郎先生
聖学院大学 政治経済学部 政治経済学科
-

消費者と事業者間がトラブルなく、安全・安心して暮らす法律を考える
福島成洋先生
明治学院大学 法学部 消費情報環境法学科
-
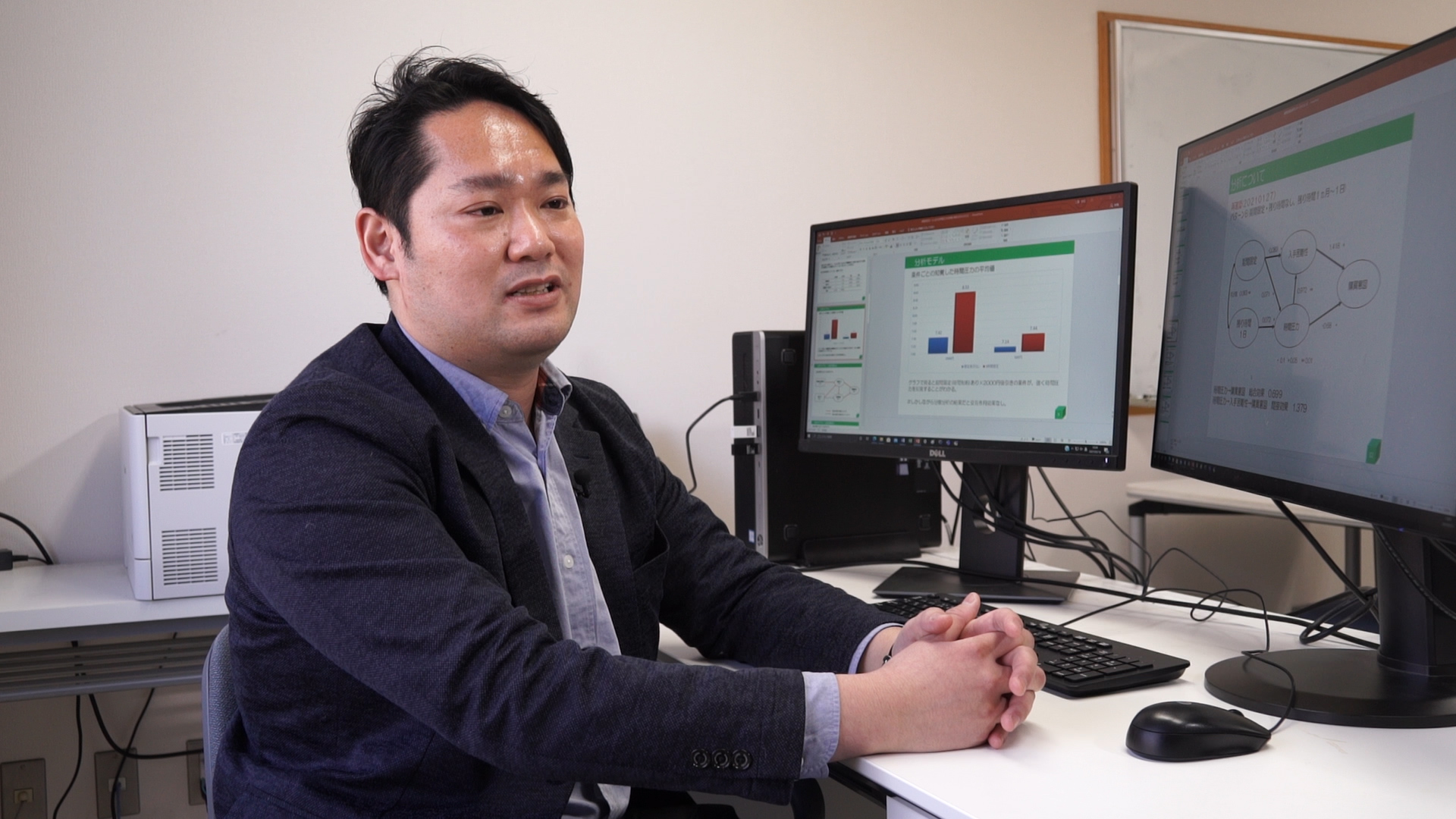
商品購入時の消費者心理を分析!
三富悠紀先生
高崎経済大学 経済学部 経営学科
-

文化や歴史を生かした魅力的な地域づくり
菊地淑人先生
山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科
-

グローバルな視点で持続可能な社会の実現をめざす
石井雅章先生
神田外語大学 グローバル・リベラルアーツ学部 グローバル・リベラルアーツ学科
-

知識と実践をつなげよりよい未来への手引書をつくる
鈴木直喜先生
清泉女子大学 文学部 地球市民学科
-

子どもが物事を理解するメカニズムを明らかにする
石橋優美先生
埼玉学園大学 人間学部 子ども発達学科
-

子どもの思いを受け止め、学級のあり方を考える
増田修治先生
白梅学園大学 子ども学部 教育学科(仮称*)
* 2024 年4 月開設に向けて設置申請中 -

健康を維持するために必要な「食」を追究!
坂本香織先生
女子栄養大学 栄養学部 実践栄養学科
-

絵とシンプルな言葉で表現する絵本の可能性を追究
正木賢一先生
東京学芸大学 芸術・スポーツ科学系
-

新興国の支援活動を通じて、社会を変革する
藤掛洋子先生
横浜国立大学 都市科学部 都市社会共生学科
-
遊びと生活動作の関係を探り、子どもの「できる」を増やす
佐々木清子先生
東京保健医療専門職大学 リハビリテーション学部 作業療法学科
-

アスリートのケガを治し、競技能力の回復をサポート!
鎌田浩史先生
筑波大学 医学医療系 整形外科
-
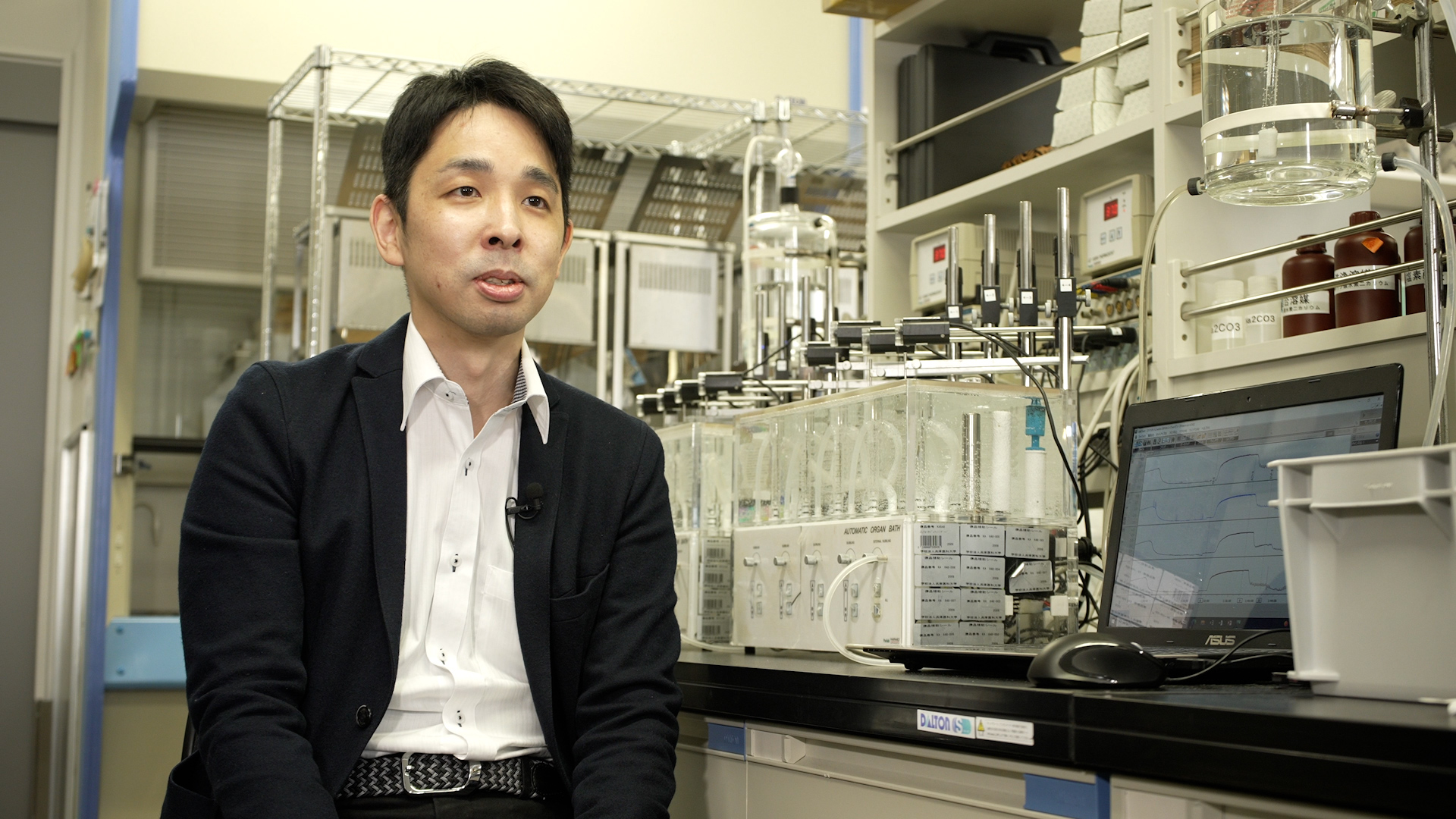
薬が作用するしくみを明らかにする
小渕修平先生
兵庫医科大学 薬学部 医療薬学科
-

コムギの遺伝子を探り、よりよい品種の開発につなげる
坂 智広先生
横浜市立大学 理学部 理学科
-
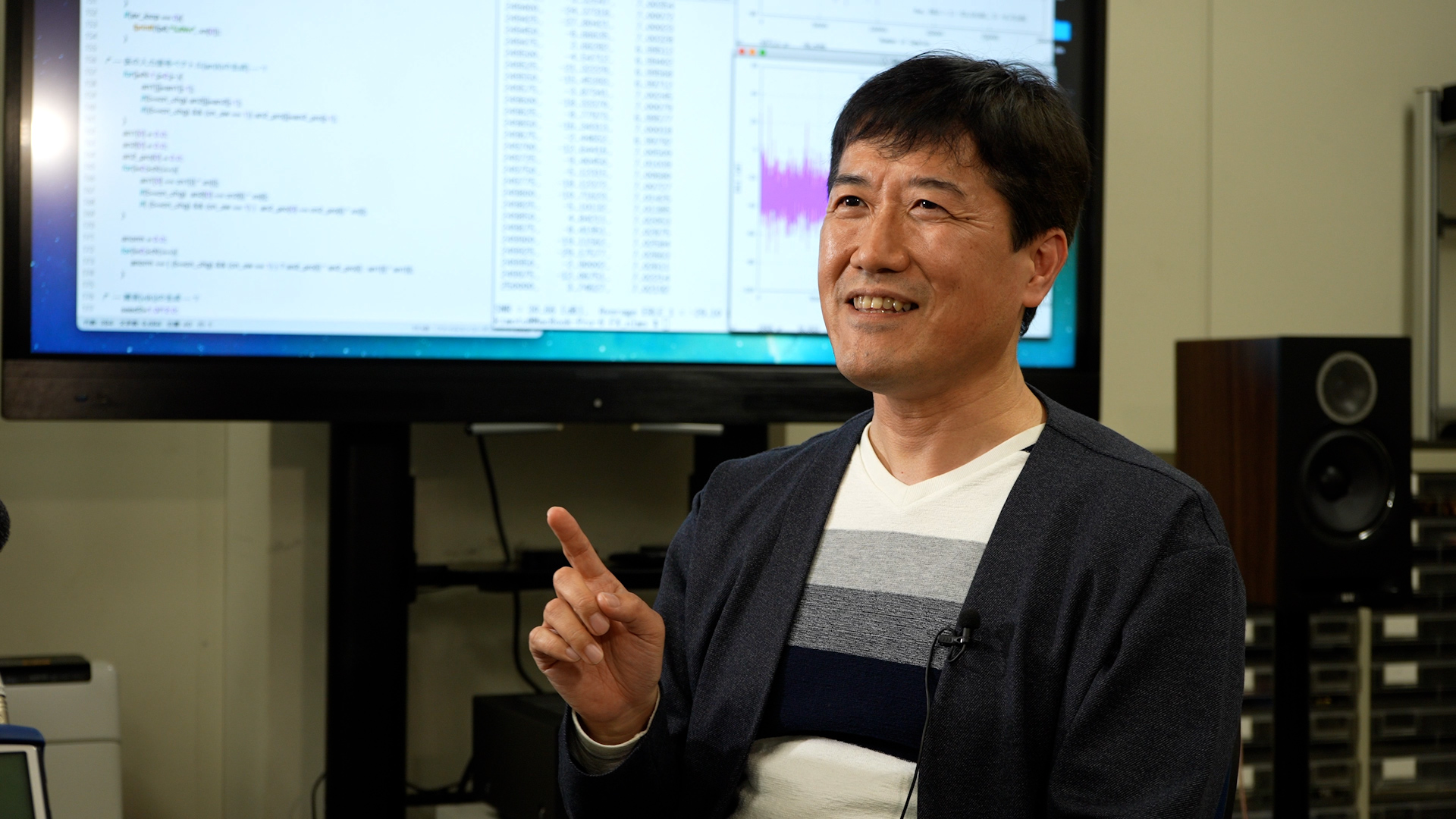
デジタル信号処理で、社会に役立つ技術を生み出す
木許雅則先生
日本工業大学 基幹工学部 電気電子通信工学科
-
海洋ごみの実態を調査し海洋資源の持続的利用をめざす
内田圭一先生
東京海洋大学 海洋資源環境学部 海洋資源エネルギー学科


