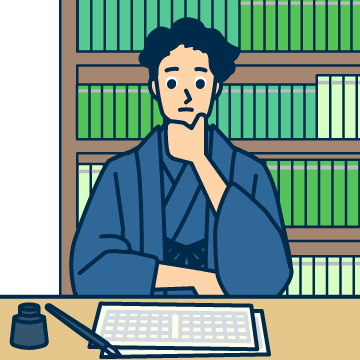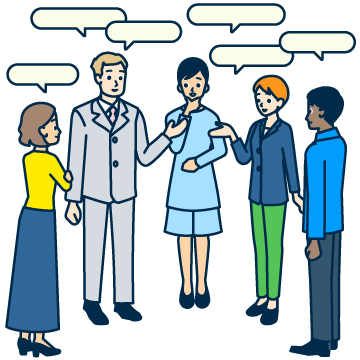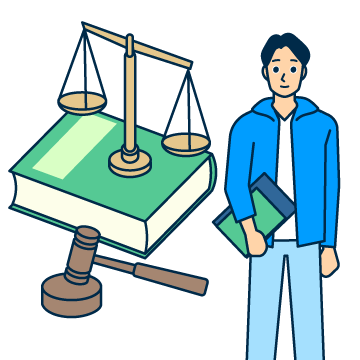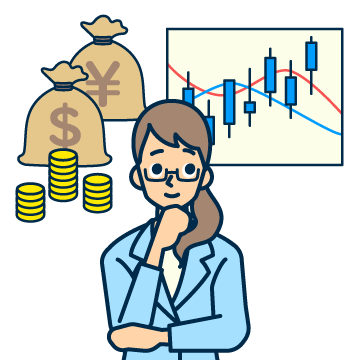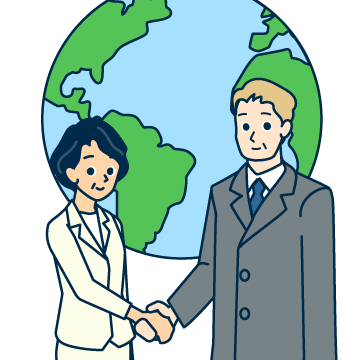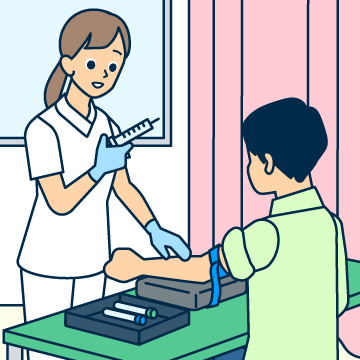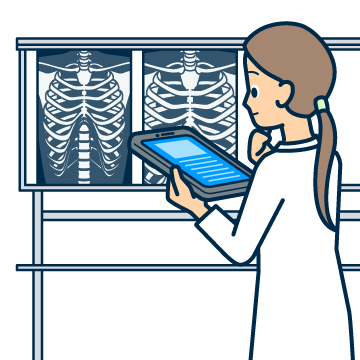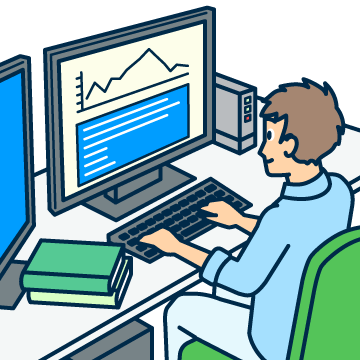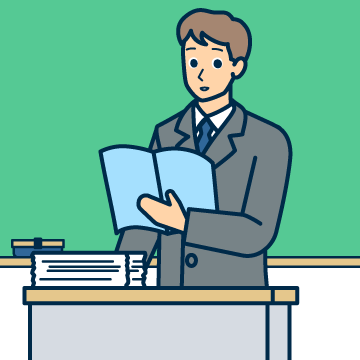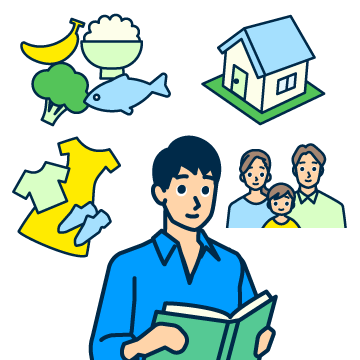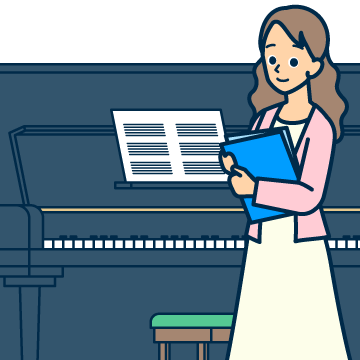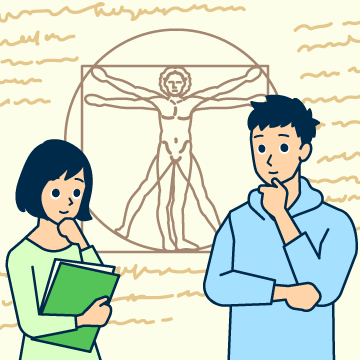考古学・文化財学
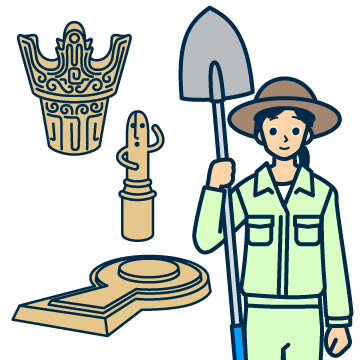
この学問についてチェックしたいポイント
関連する情報を調べる
この学問を学んでいる先生のインタビュー
考古学・文化財学 学問の内容
過去のさまざまな事象を系統的、総合的にとらえる
考古学は古代の遺物や遺跡、史跡を研究し、古代人類の文化、生活の解明を試みる学問。机上の研究にとどまらず、実際に現地に赴き、フィールドワークを行うことが多い。
文化財学は歴史遺産や、美術工芸品、建築物などの保存・修復技術などについて学ぶ学問。こちらも文化財などのある地域に直接赴き、実地での活動をすることが多い。また、近年では調査機材の発達によって、遺跡や史跡などの新たな発見が多くなっている。
考古学・文化財学 大学選びのアドバイス
考古学・文化財学の場合、大学によって得意とする分野が、日本の弥生時代、古代エジプト、メソポタミア文明など、全く異なるのが特徴だ。また、発掘調査など実地の研究が大切な学問なので、4年間でどのくらい発掘調査を行うことができるのか、場所はどのようなところなのか、最新の設備が整備されているかどうかも調べておくといいだろう。
司書や学芸員の資格取得をめざす人は、必要な科目を履修できるかどうかチェックしたい。
考古学・文化財学 時間割例&カリキュラム
座学からフィールドワークまで
考古学・文化財学は、文化学、歴史学とも密接な学問なので、1年次には歴史系列や美術系列の専門科目を課している大学が多い。2年次以降、古文書学や保存科学、環境歴史学などを扱った専門性の高い科目を学び、フィールドワークや美術館見学などの実地活動も行う。
最近では、研究に欠かせない機器を扱うための講座が設けられ、幅広い視野で情報の分析と発信を行うことのできるスペシャリストの養成をめざす大学も現れている。
先輩の時間割例
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学概論I | 保存科学実習 | ||||
| 2 | 博物館機能論 | |||||
| 3 | 博物館学総論 | 古文書学演習I | ||||
| 4 | 古文書実習 | 日本史C | ||||
| 5 | 日本史概説I | 世界女性史研究I | ||||
| 6 | 教育原論I |
考古学・文化財学 卒業後の進路
卒業後の進路として、大学院に進み研究者や大学教員をめざす人が多い。また、修得した資料の収集・保管・展示能力を生かし、学芸員などになる人や、公務員になり市町村の職員として遺跡の発掘にあたる人、歴史や文化財関連の出版社などに就職する人がいる。しかし、多くの人は一般企業に就職している。