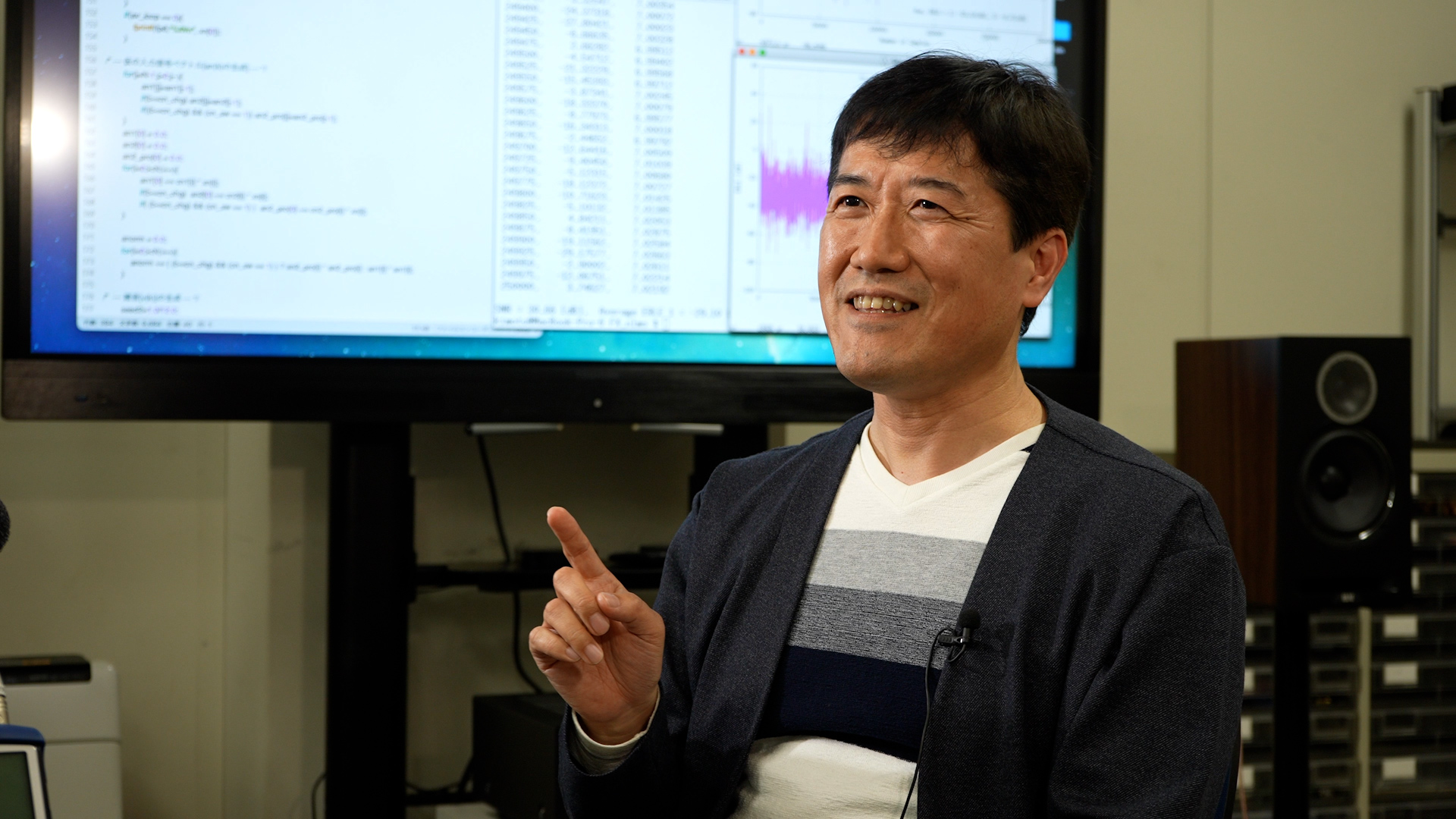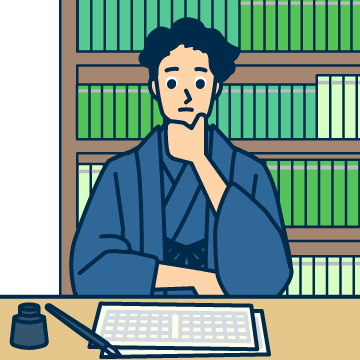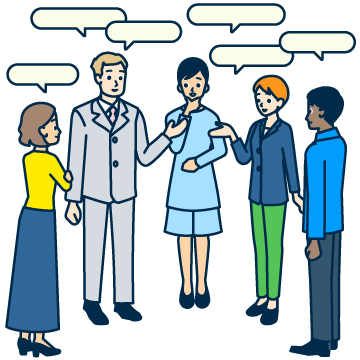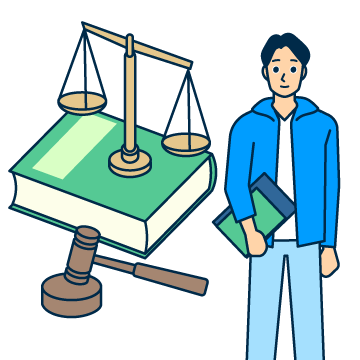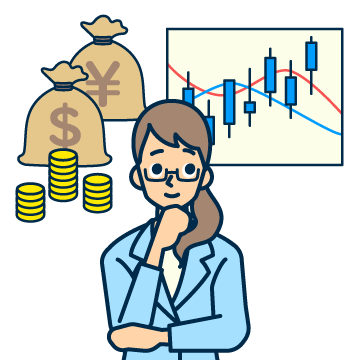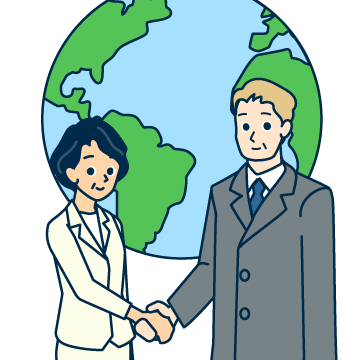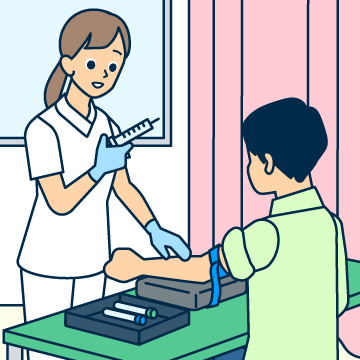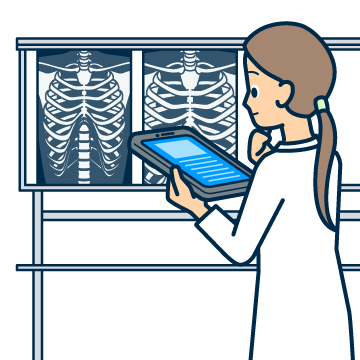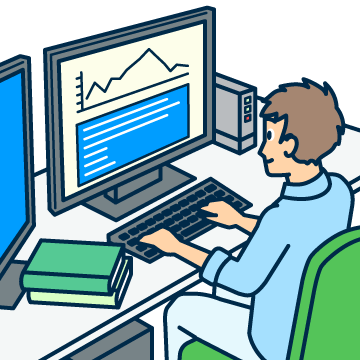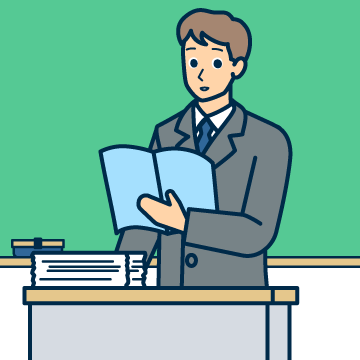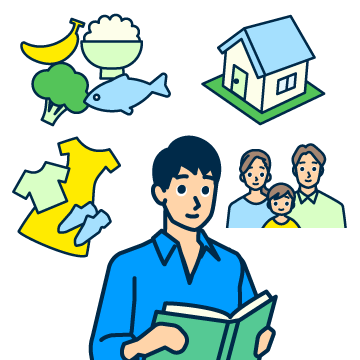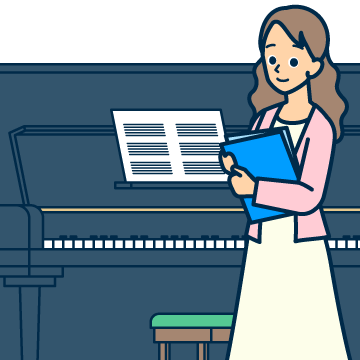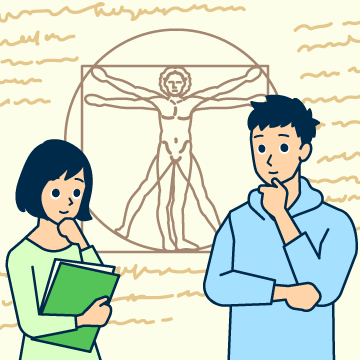工業デザイン
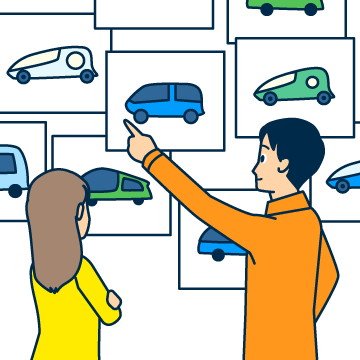
この学問についてチェックしたいポイント
関連する情報を調べる
この学問を学んでいる先生のインタビュー
工業デザイン 学問の内容
人間と工学との接点をデザインする
自動車や家電製品、工業機器から文房具にいたるまで、私たちの身の回りにはさまざまな工業製品があり、どれも視覚に強く訴えるような目新しいデザインや使いやすさの工夫がなされています。また、公共の空間や建物にも新しいデザインや機能を持つものが増えています。デザイン工学は、高度化・多様化する消費者のニーズにこたえ、機能性とデザイン性の両方を重視した製品を追求する学問です。
実際にデザインする際には、CAD(キャド)と呼ばれるコンピュータ用のソフトウェアを使って設計します。この技術は、自動車の複雑な流線型のラインなどがコンピュータで描け、反対側の側面を映し出したり、修正したり、拡大縮小したりといったことが自由にできることから多用されており、今や欠かせないものとなっています。
科学技術の進歩によって、製品のデザインもより自由な発想ができるようになりました。今後は、消費者の多様な好みを反映させた製品の開発が求められるでしょう。一方で、再利用できる材料を使用するなど環境保護に配慮したデザインや、誰もが使いやすいユニバーサルデザインの考え方を取り入れた製品へのニーズも高まっています。機能性や見た目の美しさだけでなく、環境問題や高齢化といった社会の動きに対応したデザインを考えていくことも重要な課題と言えます。
工業デザイン 大学選びのアドバイス
工業デザインは、工学部や造形学部、または芸術学部などにある学科で学んでいく。各大学の学部で、学びたい分野を扱っているのか、大学案内などで慎重に調べたい。
工学系に設置されている学科が工業製品に関する理論と実践を中心に扱うのに対し、芸術系にある学科は、芸術の一環としてのデザインをより重視している。どちらも工業デザインを扱うことには変わりないが、重点の置き方が異なる。自分がどちらの傾向にあるのか、知っておく必要があるだろう。
また、この分野はコンピュータを使った作業が多い学問。大学選びでは設備が整っているかどうかも重要だ。
工業デザイン 時間割例&カリキュラム
デザイン学と工学をあわせて学ぶ
デザイン工学では、工業デザイン、ビジュアルデザイン、空間デザイン、サイン計画などの工業デザイナー養成のための科目とともに、人間工学や材料計画、製品開発計画、デザイン解析、視覚・環境計画などの科目を履修するのが一般的です。また、専門科目として造形論、製品計画論、環境生理学などを履修する場合もあります。
いずれの場合においても実習は大切な科目になっており、寺や公園など、記憶に残る心地よい空間をスケッチしたり、実際に見に行ったりする実習や、特定の年代に使いやすいマウスのデザインをテーマに模型を作るという実習を行う大学もあります。
先輩の時間割例
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 構造設計III | 建築生産 | ||||
| 2 | 構造設計演習 | 施設計画 マネジメント デザイン |
地理学 | 製品デザイン論 | 建築エスキース | |
| 3 | 英語 | 統計学 | 施設計画 マネジメント演習 |
英語 | ||
| 4 | 構造力学II | 微積分学 | 建築デザイン 総合指導 |
|||
| 5 | 都市環境 デザイン |
構造力学演習 | 構造設計II | 建築設計 プロセス |
工業デザイン 卒業後の進路
工業デザイン、グラフィック、環境設計、インテリアなどの業種に進み、専門性を生かした仕事に就く人が多くなっている。例えば建設会社で景観をデザインしたり、各種メーカーで、企画・開発担当者となるなど、活躍の場は幅広い。また、それらの会社などで経験を積んだ後、独立してインダストリアルデザイナーとなる道も開かれている。