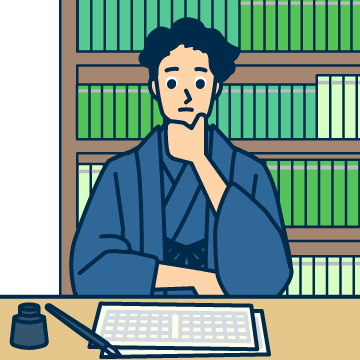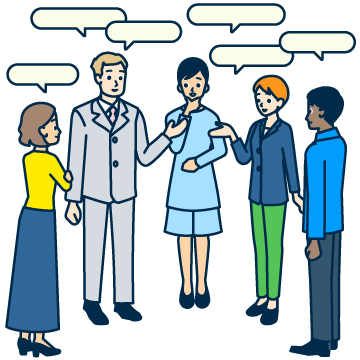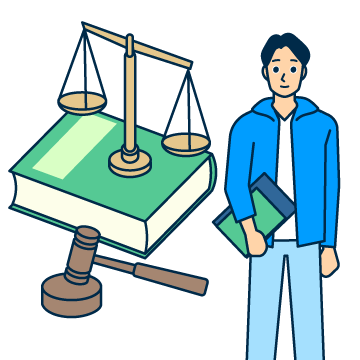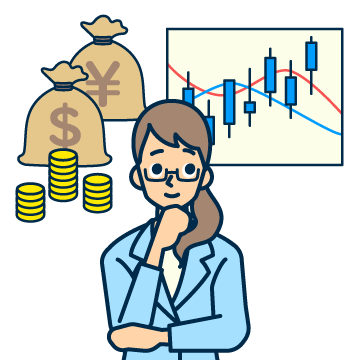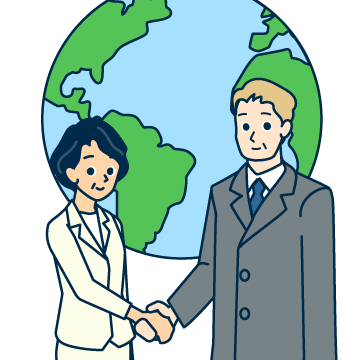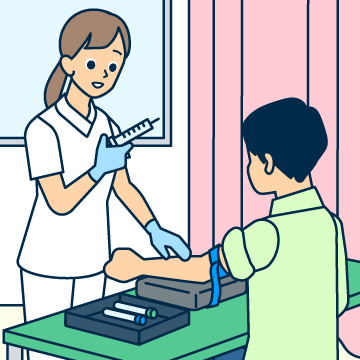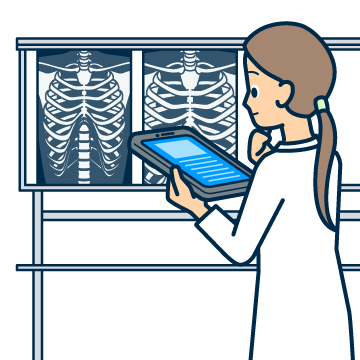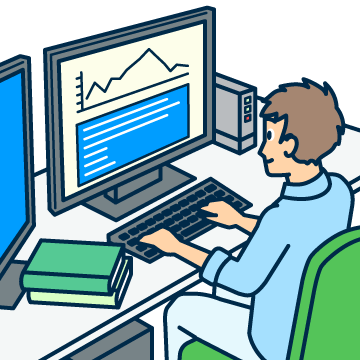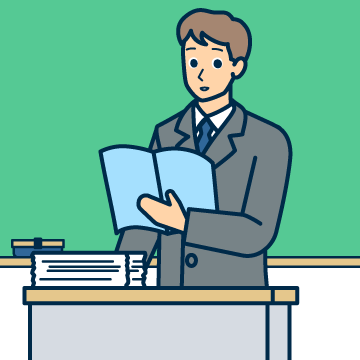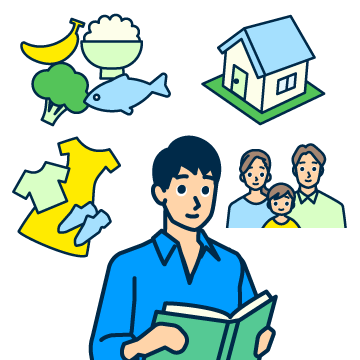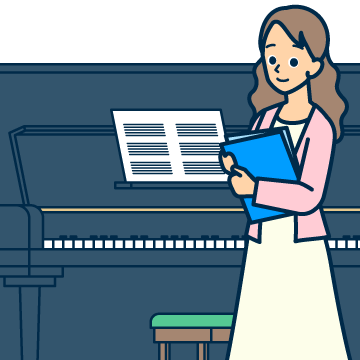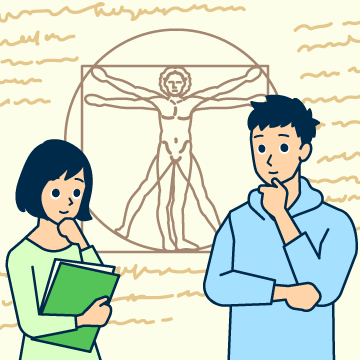農芸化学
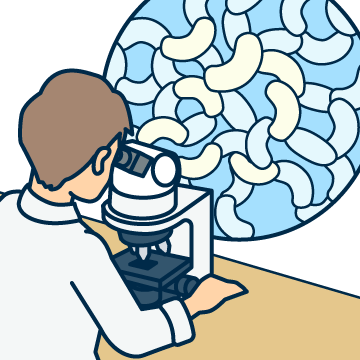
この学問についてチェックしたいポイント
関連する情報を調べる
この学問を学んでいる先生のインタビュー
農芸化学 学問の内容
農業発展のために、技術と薬品を開発する
農芸化学は、農産物の生産から加工、保存、そして廃棄、再生というサイクルを、生物化学や有機化学などから研究していく、実験科学的な要素が強い学問分野です。
具体的な研究分野としては、栽培のための土壌に関する分野、肥料や農薬に関する分野、微生物の応用に関する分野、食品を栄養学的に解明していく分野、食品の加工・保存に関する分野に分かれます。
農芸化学では非常に複雑な実験が伴いますが、それだけに研究成果への期待も大きいものがあります。例えば、食物と微生物を利用して、石油に代わる新エネルギーの開発が進められています。また環境保全の問題では、生ゴミを発酵させて資源にする研究や、生分解性プラスチックの研究が注目されています。このプラスチックは微生物の働きによって簡単に分解されることから、洗剤や包装材、食品添加物などへの応用が期待されています。
農芸化学は、常に農業を発展させるために新しい技術や薬品を開発してきました。将来の人口増大に伴う食糧不足が重大な問題となっている今こそ、農芸化学には、人間生活をより豊かにするための高度な技術が求められているのです。
農芸化学 大学選びのアドバイス
農芸化学は主に農学部の学科で学ぶことができる。しかし、他の農学系の学部でも、関連する科目が履修できる場合や、入学後にコースを選択できる場合もある。大学案内などで調べておくとよい。
また、大学によって研究内容が異なる。醸造や畜産食品といった研究を専門に扱う学科もあるので、目的意識が明確な場合は必ずチェックしておこう。
実験・実習が非常に多いので、施設や設備などの充実度が、大学選びでは重要な点。最新の機器や機材があるかどうかをチェックしたい。
研究者をめざす場合には、大学院の設置状況も調べておく必要があるだろう。
農芸化学 時間割例&カリキュラム
成分分析など実習はユニーク
農芸化学は、生物と科学を基礎とした応用科学と考えることができ、有機化学、生物化学、酵素化学、分子生物学がその土台になっています。ですから農芸化学を学ぶ際には、それぞれの科目をバランスよく学んでいくことになります。
その一方で農芸化学では、実験や実習が非常に大事なものであり、各大学で特色ある実習や演習が組み込まれています。例えば食品の一般成分・特殊成分を分析したり、がん細胞の増殖を抑える効果がある食品について学んだり、レトルト食品の加工技術について学んだりします。
先輩の時間割例
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2 | 食品加工実習 | 植物栄養学 | 土壌学 | 生活と園芸 | 社会学 | 食品化学各論 |
| 3・4 | 生物化学 | 物理化学 | 英語 コミュニケーション |
有機化学 | 応用微生物学 総論 |
|
| 5~8 | 農芸化学実験 | 農芸化学実験 | 農芸化学実験 | 農芸化学実験 | 農芸化学実験 |
農芸化学 卒業後の進路
食品、医薬品や化粧品などのメーカー、化学工業などの一般企業で、研究者や技術者となる人が多い。これらはバイオテクノロジーの発展により、今後も有望であると言える。
また、大学院へ進学する人のほか、国家公務員や国公立の試験研究機関の職員、食品関係の公共団体の職員となり、研究職に就く人もいる。