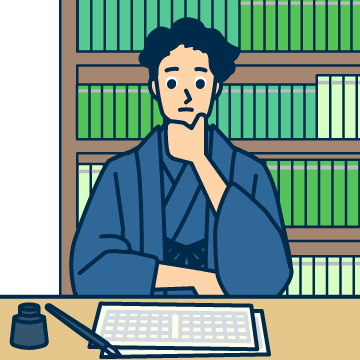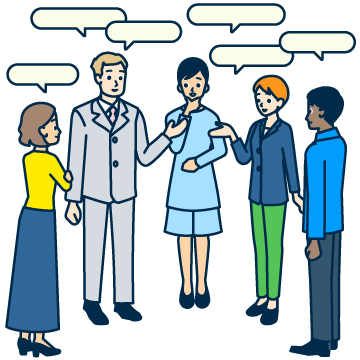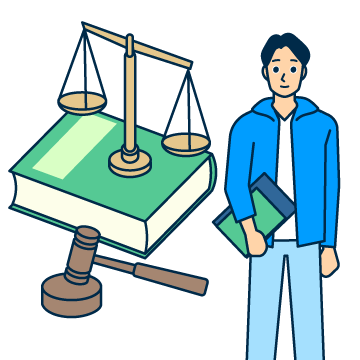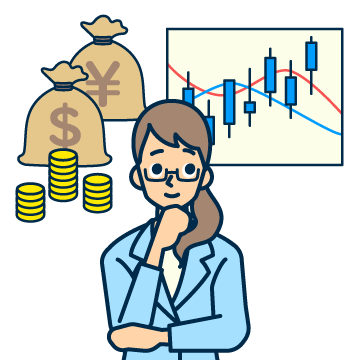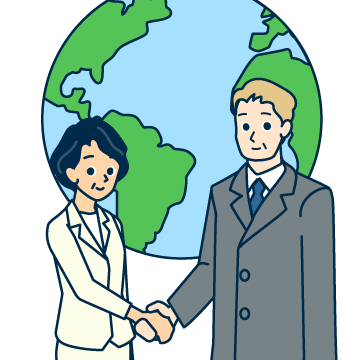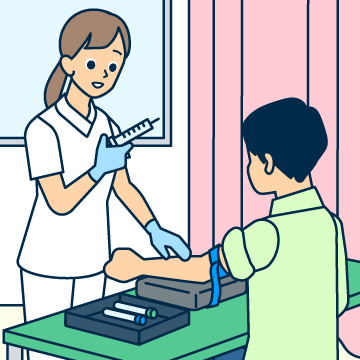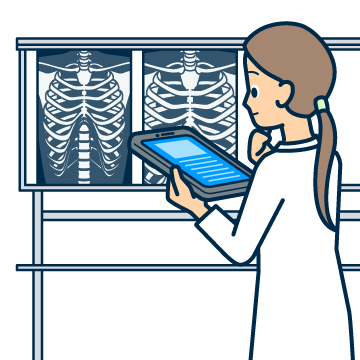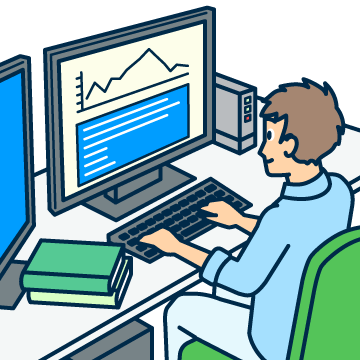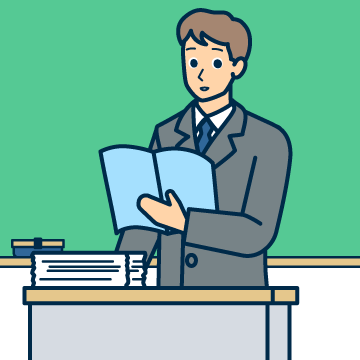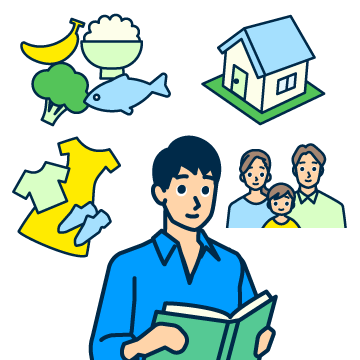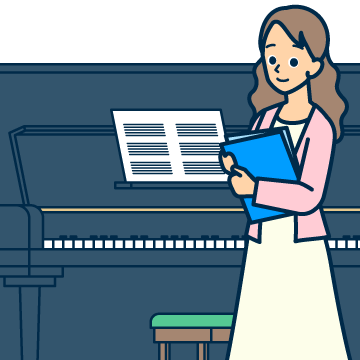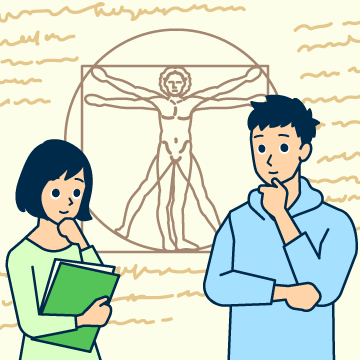水産学
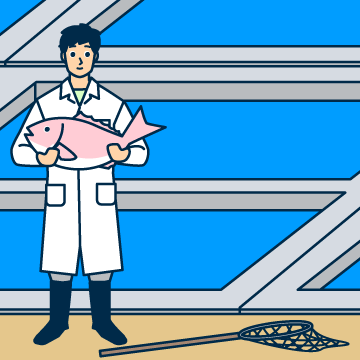
この学問についてチェックしたいポイント
関連する情報を調べる
この学問を学んでいる先生のインタビュー
水産学 学問の内容
水産資源の有効利用を科学的に追究する
水産業は、海洋や川、湖沼に生息する生物にかかわる分野を受け持つ産業です。水産学は、その水産生物資源の適正な生産と有効利用を、科学的に追求していく学問であるといえます。
水産学を大きく分けると、天然の生物資源の捕獲手段を科学的に体系化していく「漁業学」、海洋生物を人為的に育成したり、その成長や病気などを扱う「増殖学」、水圏の生物を食糧として加工・保存していく「食品生産学」の三つの分野に分かれます。
漁業学では、人工衛星による漁場探索の方法や工学的技術を用いた作業の省力化、また適正管理による乱獲防止の徹底や、漁具・漁法の研究開発が、現在の大きなテーマです。増殖学では、バイオテクノロジーの手法による新品種の開発や、環境に優しい漁業用新素材の研究開発が注目されています。食品生産学では未利用の水産資源の有効利用について、またバイオテクノロジーの手法を用いての食品処理・加工の効率化などが課題です。
このような研究はそれぞれ、国際間の漁業水域の問題や、乱獲・環境汚染による資源の減少、また消費者のグルメ志向など、現代社会の要請を受けて進められているのです。
水産学 大学選びのアドバイス
水産学を学べる大学は少ないが、それぞれの大学で特色あるカリキュラムを構成している。
どんなフィールドワークを行っているのか、研究施設は整っているか、実習船を所有しているか、どんな研究をしているのか、卒業生の就職先はどこなのかなどを大学案内で調べて、志望校を決めるといいだろう。
水産学 時間割例&カリキュラム
漁の実習から缶詰作りまで
水産学を学ぶ場合には、生物学、魚類学、水産植物学、水産資源学、水産経済学、水産養殖学、水産微生物学などが主要科目になります。専門的な科目としては漁業工学や水産化学、水産物理学、水産土木学、海洋公園論、航海学、化学工学、水産高分子学などがあります。
演習も多く、はえ縄漁の実習や漁業関係施設の見学、アザラシの遺伝子から親子を判定する実習など、各大学ごとにさまざまな実習が行われています。また、泊まりで海洋調査船に乗って海水や生物の分析を行う実習をしている大学もあります。
先輩の時間割例
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育 | アイルランド 紛争と文学 |
||||
| 2 | 英語 | 西洋史入門 | ||||
| 3 | 海洋生物の化学 | |||||
| 4 | 海洋測位学基礎 | 水産食品の化学 | ||||
| 5 | 海洋社会情報論 |
水産学 卒業後の進路
水産会社をはじめとした食品メーカーに就職する人が多いが、情報処理、流通、金融など、幅広い分野への進出が増えている。一般企業ではほかに環境アセスメント、医薬品・化学工業、船舶関連などにも就職している。
水産関連の研究所の職員や農林水産省など官公庁の公務員も人気が高いが、どれも研究職は難関である。