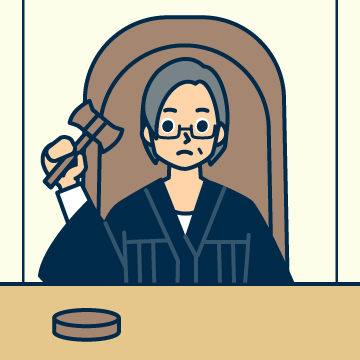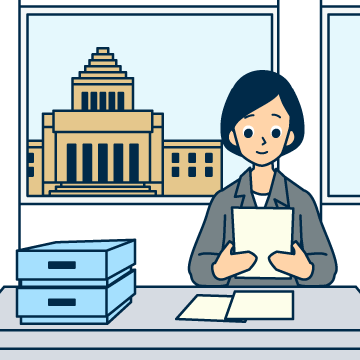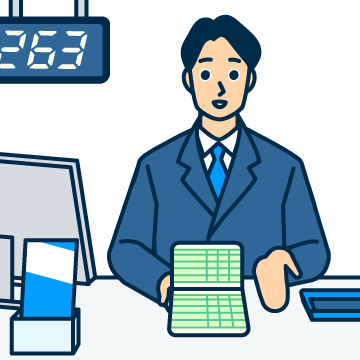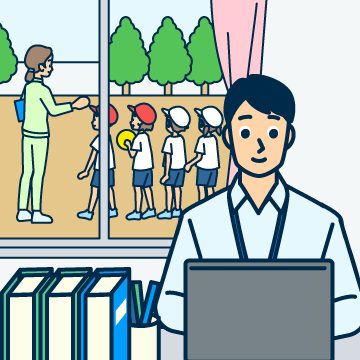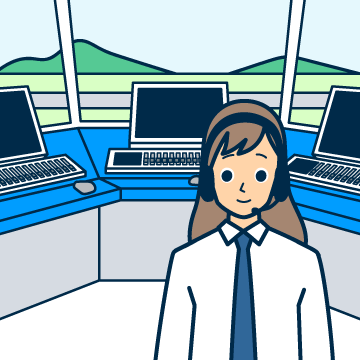電気工事士の資格
いろいろな視点から
この職業について調べてみよう
電気工事士の資格
必須資格 … 電気工事士
電気工事士として働くためには、国家試験の合格者に与えられる「電気工事士」の資格が必要だ。資格には第一種と第二種があり、第一種の方が作業を認められる範囲が広い。2023年度国家試験の合格者数は、第一種が年間約1.6万人、第二種が約6.8万人。合格率は第一種が約35%、第二種が約39%とあまり高くない。ただし、電気工事士になる間口を広げるために、第二種の試験は年間2回受験できるようになっており、筆記試験に合格した場合、仮に技能試験が不合格でも、次回受験時の筆記試験は免除される。合格率は高くなくても、チャンスの多い試験だと言っていいだろう。
そのほかにあると便利な資格
○高所作業車運転技能講習修了
高所作業車の運転に必要な学科・技能講習。架空線の作業をはじめ、高いところでの作業には高所作業車が必要になる場面があり、重要度は高い。
○消防設備士
火災報知器やスプリンクラーといった消防設備の点検・整備を行うために必要な資格。甲種と乙種の2種類がある。甲種を所持している場合、工事や点検、整備など、消防設備に関するすべての作業を行える。乙種を所持している場合、消防設備の点検と整備のみ行える。火災報知器等も配電が必要な設備であり、電気工事士として仕事の幅を広げるうえで役立つ資格だ。
なお、電気工事士の資格を所持している人は一部の試験科目が免除される。
※甲種・乙種とも、免状に指定されている消防設備が対象。
○電気工事施工管理技士
工事計画の立案や施工図(工事の設計図)の作成、品質や安全の管理を行うための資格。1級と2級があり、2級は第一種電気工事士の資格を所持している場合は実務経験なしで、第二種電気工事士の資格を所持している場合は1年以上の実務経験があれば受験できる。
電気工事の監督業を行ううえで、必須と言える資格。取得すれば大きなキャリアアップをめざせる。
※電気工事施工管理技士は、2024年4月より、建設業法に基づき受験資格が改正された。上記は旧受験資格。新受験資格では、1級の第一次検定に年齢設定が追加され、また、1級・2級の第二次検定は第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受験可能となった。ただし、2028年度までは旧受験資格と新受験資格の選択が可能である。
関連する職業
機械系研究・技術者/電子、電気系研究・技術者/エネルギー系研究・技術者/化学系研究・技術者/企業内研究員
電気工事士に関連した職業は、研究職や技術職の中から見つけることができる。機械の工事・点検などを行うことから、機械の開発や製造に携わる機械系の研究・技術者、電子・電気系の研究・技術者は特に近い職業と言っていいだろう。電気工事士に興味があるなら、以下に挙げた職業にも興味を持てるかもしれない。
オープンキャンパス情報を調べる
みんなが興味を持っている
職業は?
他の職業もチェックしてみよう!
 対人サービス系
対人サービス系
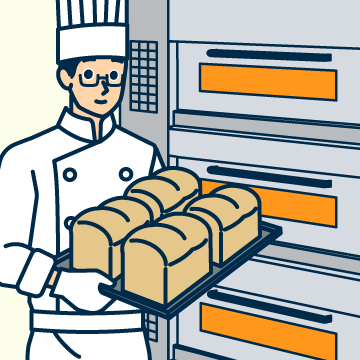 技能サービス系
技能サービス系
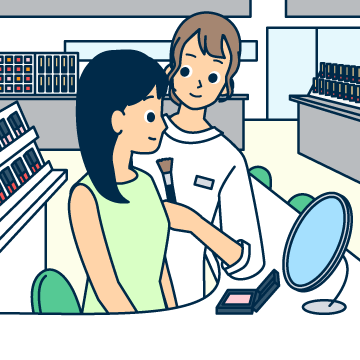 営業・販売系
営業・販売系
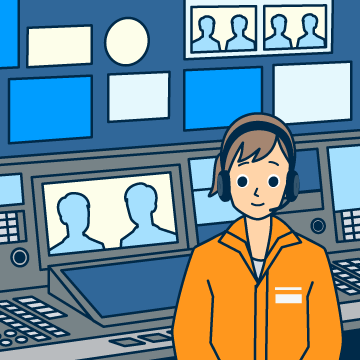 マスコミ系
マスコミ系
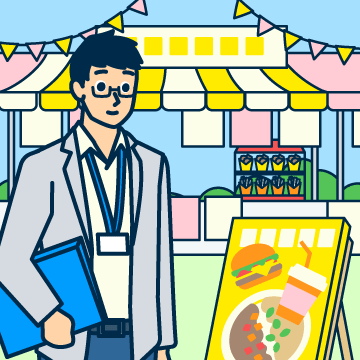 企画調査系
企画調査系
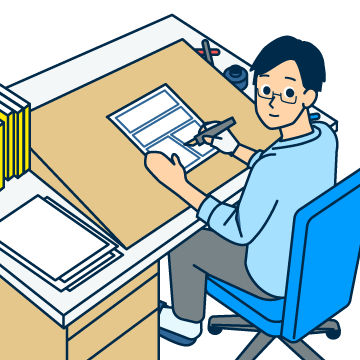 芸能・芸術系
芸能・芸術系
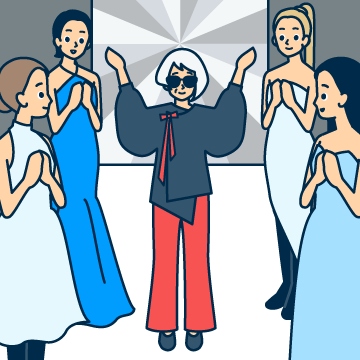 デザイン系
デザイン系
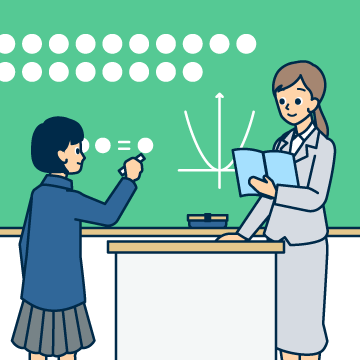 教育系
教育系
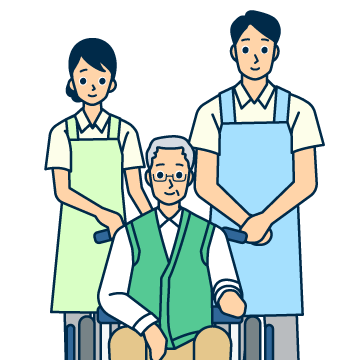 社会福祉系
社会福祉系
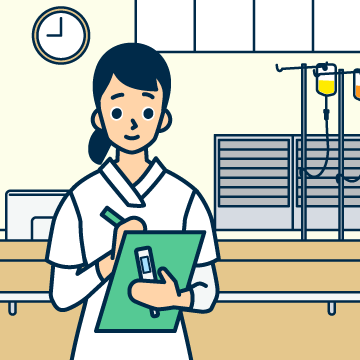 医療・看護系
医療・看護系
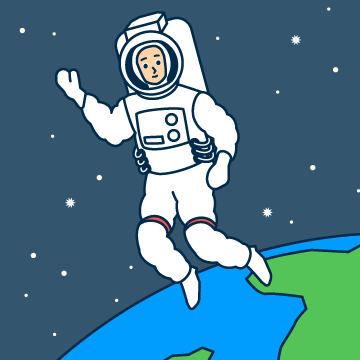 自然研究・技術系
自然研究・技術系
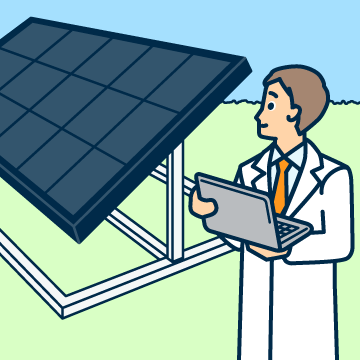 機械・化学研究・技術系
機械・化学研究・技術系
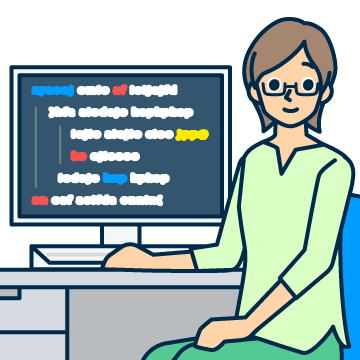 コンピューター系
コンピューター系